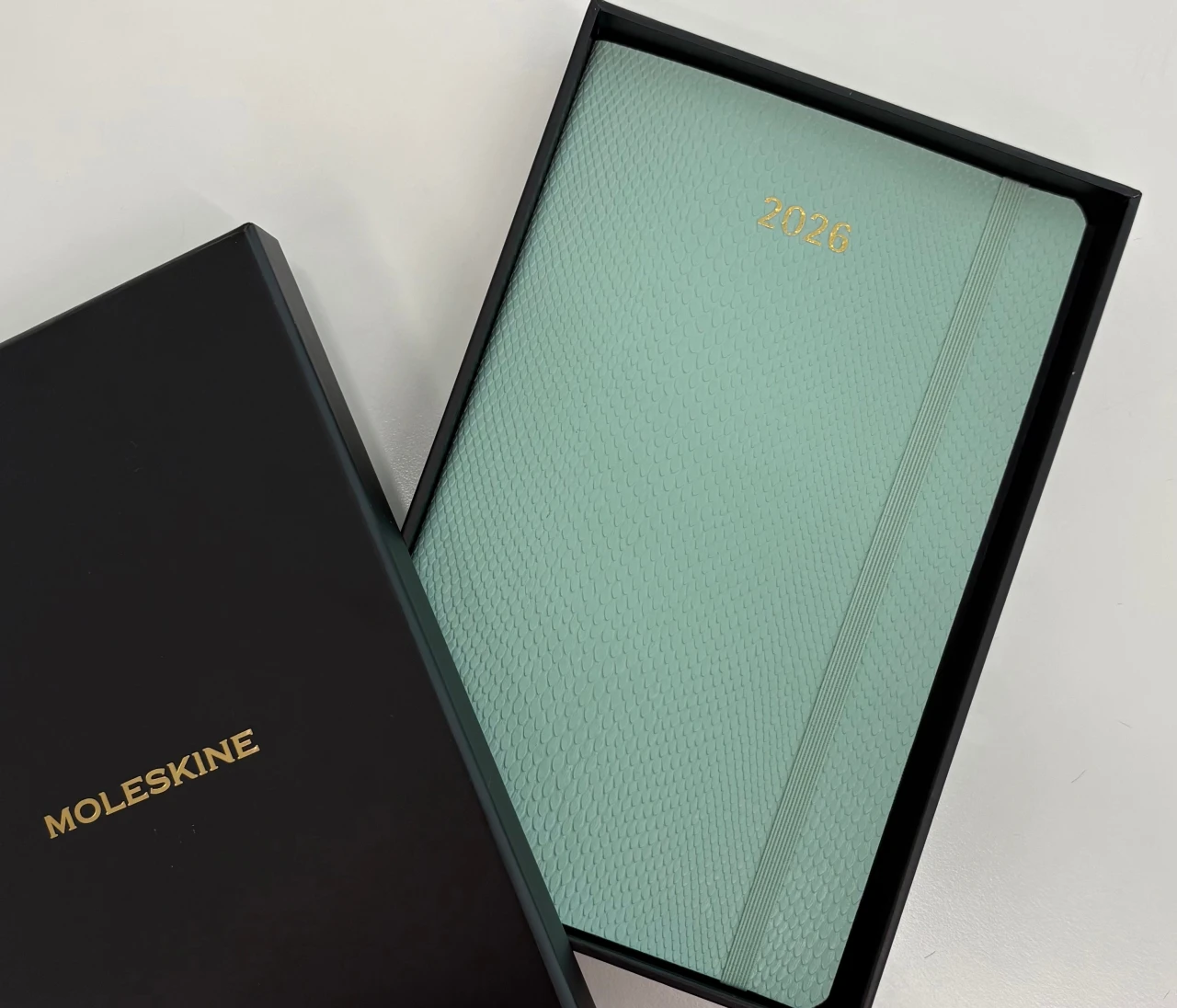CONTENTS
▶購入派が正解だった15年
日本の住宅の大半、特に地方や木造の戸建住宅は建築後20~25年程度で、経済価値は0になると言われており、耐久消費財として捉えるのが一般的です。
更地に戻す費用も入れると、0どころかお金を払わないと買い手がつかないような住宅はたくさんあります。そのため、空き家になります。
世田谷区も、実は空き家の数が全国一です。土地の流通価格はきちんとつくエリアですが、相続人が住みたいほどではなく、もしくは複数の相続人が協議してまで分けても高値というほどではないからです。これが麻布台ヒルズの用地であれば放置されていませんから、デベロッパーも魅力を感じていないわけです。
また、日本の人口は減る一方なので家を買うなど馬鹿げている、家なんていっぱいある。という主張は少なくとも私が社会人になった10年前から根強く、賃貸vs購入トークでも必ず見かけます。
10年経ちますが、東京のマンション価格は1.5倍は上がりました、人気のエリア・物件では2、3倍以上になりました。
地方でも、例えば北海道の人口は減り続けていますが札幌には人が流入し、不動産価格は上昇しています。この集約の現象は各地で見られますし、日本の人口減で東京の不動産価格が上昇、というのは理屈としておかしくありません。
資産性とは誰かがそれに価値を感じ、相応のお金を出してくれればあると言えます。不動産は立地がかなりの割合を占めるといっていいでしょう。
不動産に詳しい方の多くは、不動産自体に詳しいのであり、資産価値についても、過去からの推移と現状の分析に優れていますが、マクロの視点から将来性を考えるのはまた別の能力です。
特に特定の街に深いネットワークを持つような場合、愛着があるので東京のニューカマーの価値観に否定的になりがちです。
各上場企業の社員が自社の株価の変動を当てられるわけではないのと一緒です。
▶今後15年は立地と面積にすぐれた中古マンションを選別したい
最近23区新築マンションの平均価格が1億円を超えたことで、これまでの暴落論調と打って変わり新築・新開発が出たら急げと買い煽りをする人が増えています。
落ち着いてください。
上昇局面ならそれでいいのですが、一般向けのなんちゃって億ションは将来的に厳しくなります。富裕層向けの物件は伸びしろがあるとしても、一般の給与所得者のてっぺんを読み違えると、無い袖は振れないので、今トレンドの中途半端な広さの物件は思うような価格がつかなくなる可能性があります。
また、安物買いの銭失いで、都内ならどこでもいいわけではありません。
上昇局面でも値上がりしなかったエリアは基本手を出してはいけません。人気のなさにはちゃんと理由があり、いわば婚活女性がこのレベルと結婚するくらいなら結婚しないほうがよい、と判断するような物件ですから、この先参入者が増えても期待できません。
同じエリア内でも、タワマンの上昇が板マンよりずっと激しく、タワマン選好の流れは続くとみています。中でも、ベイエリアにネガティブイメージを持っていた東京のひと昔前の世代が減る一方なことで、コペルニクス的転回によってベイエリアやトーキョーイーストは適正評価を得て人気はさらに加速するでしょう。
いつの世も新しい価値観を決めるのは天動説信者ではありません。
港区内陸部にしか住めないと言っていたはずの人も、芝浦に引っ越し後もぴんぴんしていますし、新築にしか住めない体質だったはずの人も、ファミリーサイズを探し出した途端冷静に予算を鑑みて立地と面積で中古を選び元気に暮らしています。
この新しいトレンドを踏まえた上で、実需から明らかに離れていない、という大原則のもとに与信をいっぱいに使い、手が届かないような物件を無理に買うくらいが正解です。
▶トレンドの変化、横と縦の軸で比較
1億2千万~1億5千万くらいが一般所得者のガラスの天井で、トレンドに変化が起きると推定しています。
この15年ほどのトレンドは、
立地は
・都心回帰
・駅近
物件のトレンドは、
・注目度高い新築
・狭め
でした。
どのあたりがガラスの天井か、横と縦の軸で見てみたいと思います。
ひとつの統計手段として「年収倍率」があります。要は「所得と不動産価格の乖離をチェック」するためですが、国によって統計基準が違うので単純比較は難しいところ。お遊びに見てみましょう。
アメリカやイギリスは世界中から資金が流入しており、日本との比較としてはあてにならないでしょう。カナダ、シンガポール、オーストラリア等の一部の大都市では外国人の不動産投資に制限がかかるほどチャイナマネーが入っており東京とは状況が違います。
地理的にも近く自国民だけで価格が動いてる中韓が比較対象としてよさそうです。
横比較
ソウル 約17~19倍
深セン 約35倍
上海 約25倍
東京新築 約13倍
(個人的な感覚)東京圏約7~ 8倍
東京の場合、神奈川、埼玉、千葉でも上記他都市アクセスが叶うので東京圏の場率は7倍程度で、肌感覚でも実需に即していると思います。
中韓は平均的な給料ではすべてを貯金に回しても数十年間かかるという絶望的な倍率に。日本と比べ格差が大きいこともありますが、なんといっても結婚時に男性が家を用意する習慣があり、購入時に親がお金を出すのが一般的になっているのが大きいです。
東京でそうなる可能性はないでしょう。まわりを見渡しても女性側のほうが彼氏に結婚してもらおうと画策することが多く、男性の親が家を用意するケースはあっても、息子の所得をはるかに超えた援助をするのはあまり見かけません。
日本人の富裕層の大多数が55歳以上のシニアであるというデータが示すように、富裕層の出身であっても(資産の譲渡のタイミングが相続の時と遅いため)、本人は2,30代の一次取得時では富裕層にはならず、親が援助しても数千万だけで、結婚して子どもがいても普通のサラリーマンが買える程度の家で暮らしています。
親が資産家の知人をみても、資産の額から中国の基準で言えば親が10億くらいの家を買ってあげるものですが、彼は親が用意した1億程度の家でつつましく暮らしています。
富裕層の親が桁違いの援助をしなければ無い袖は振れませんから、中韓との比較は意味がないでしょう。
東京は世界の大都市と比べ安い安いと言われますが、世界の大都市がたいてい地理的制約で面積が限られているのと違い、だだっぴろい関東平野にまんべんなく鉄道を引いてるので、横比較は、あまり意味のあるものではないと思います。
▶縦に10年くらい推移をみてみよう
わたしが社会人になった2014年、マンション購入に向け、不動産と株価に詳しい識者に今は買い時か尋ねました。
2011年頃に底を打った、今は回復しているが高いと思う、2011年の水準に戻ってからがいいと思うとのこと。
しかし当時家賃相場と比べ明らかに不当に安い水準でしたので、おじさんのバブル後遺症だろうと思い、参考にしませんでした。
ちなみに今から見れば格安だったこの頃、メディア等は購入なんてアホだや、人口は減る一方だぞが論調でした。
株価と不動産価格に相関関係はありますが、黒字倒産はあっても家賃20万のマンションに値段が付かないなんてことはありえません。我々の日々の生活に住居が欠かせない以上、家を借りますし、家賃より明らかに安い物件価格は適正とはいえません。
オリンピックを控えた2017年~2019年、オリンピック後に外国人投資家が金を引き上げ湾岸タワマンは大暴落!の合言葉をよく見かけました。この数年に渡って、実需のタイミングだったにも関わらず大暴落説を真に受け買い控えていた層は、少なくなかったようです。
一部メディアがセンセーショナルに書き立てた外国人投資家にとっての投資とは、一般にキャピタルゲインを狙うので、購入した部屋は空室になるはずです。仮にそうであればオリンピック後に引き上げ、それを日本人が同額で買わなければ、暴落するでしょう。
ならば夜に湾岸エリアにでも赴き、部屋の電気がついているかどうか、見ればいいだけです。
自分の足で歩き一目でも見れば、大暴落などはトンデモ言説であることは確認できたはず。
2020年~2022年を見ても、様子見していた実需層が多く、2023年やっと消化しだしたことで高騰というよりは適正な価格になったというところでしょう。
周りのサンプルを見ても、夫婦ともにサラリーマンの家庭はだいたい1億2000万くらいを目途に予算を決めています。日々の生活のキャッシュアウトを考えると、これ以上は難しいでしょう。親の援助も足せば1億5千万くらいまでが上限でしょうか。
富裕層や海外投資家の実需ではない、キャピタルゲイン狙いの購入は引き続き根強いですが、実需としての不動産市場はこれくらいがピークで、今後トレンドは面積広め、中古にシフトする可能性があります。
ファミリーの生活利便性や居住性、出口戦略両方の最大公約で、湾岸の(価格的に中古で)駅近ファミリーマンションで80平米くらいのものを選べば、底堅い実需に支えられ出口も明るいでしょう。
▶なぜおじさん向け経済紙は不動産価格暴落を唱え、タワマンアンチなのか
今30歳以上、特に40歳くらいであれば、この15年の早いタイミングで都心部やタワマンなどで購入していたら3,000万~1億以上の含み益か売却益が出ている。
しかし購入適齢期だったにも関わらず、意外と見送った人は多い。親や配偶者に反対され、タワマンやベイエリアを諦めたというエピソードもあるあるである。
中にはメディアやビジネス総合誌で人気の不動産価格暴落論を信じ、価格上昇後に途方に暮れた人たちもいるが、なぜタワマンバブル崩壊のようなコンテンツがウケたのだろうか。これらの雑誌の購読層は中年のビジネスマンがメインで、すでに購入し新たな買い替え需要がないことが多いにも関わらず、である。
ビジネス総合誌を読むような層はある程度自分の選択に自負があり、それを否定するような新たなトレンドに肯定的ではないのである。また、本物の富裕層はタワマンに住まない、というよく見かけるアンチコメントも、要はニューニッチの出現はないという願望である。15年後の価格を形成するのは今の若年層であり、これから購入を考えるなら彼らの意見に耳を傾けたい。













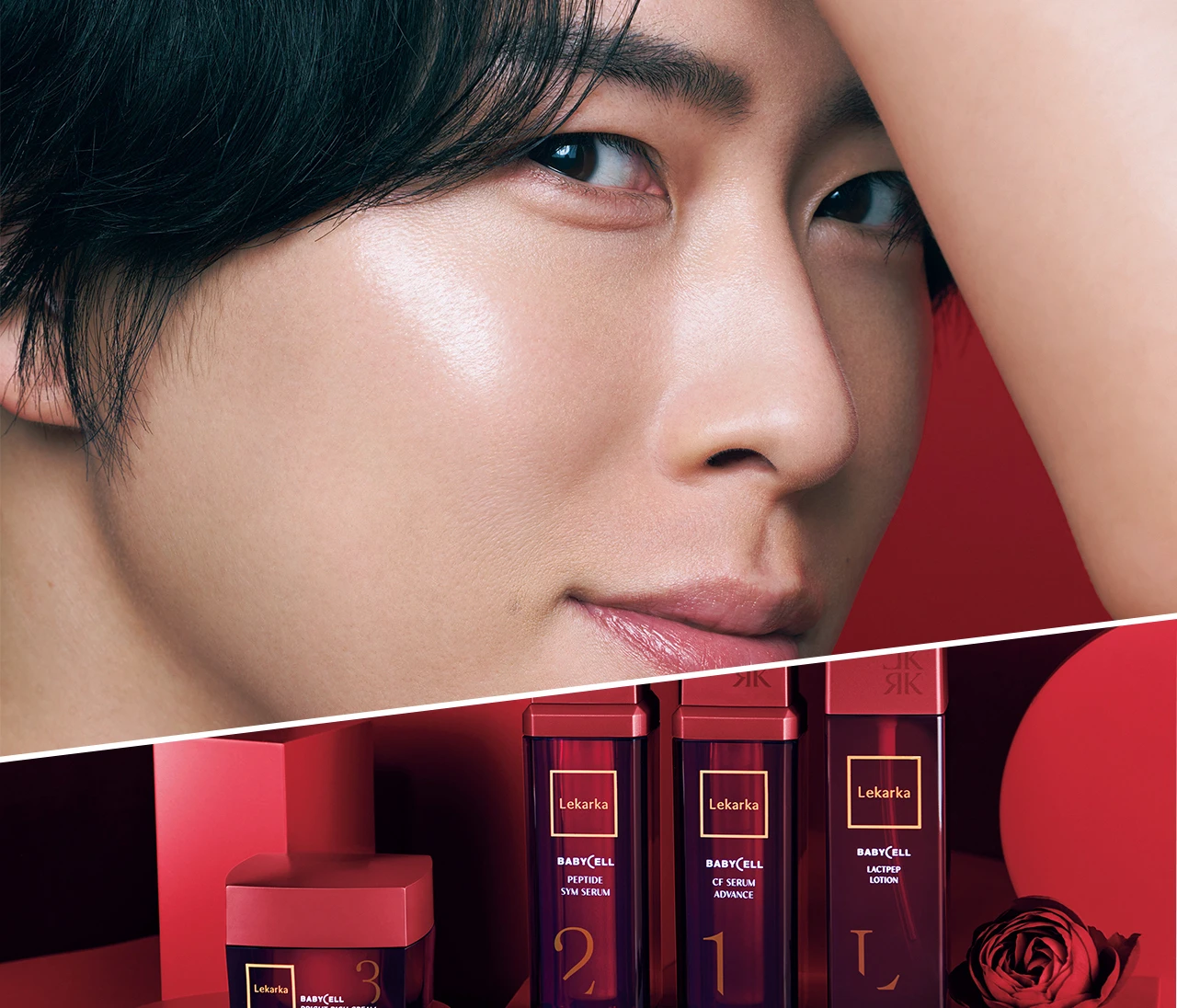








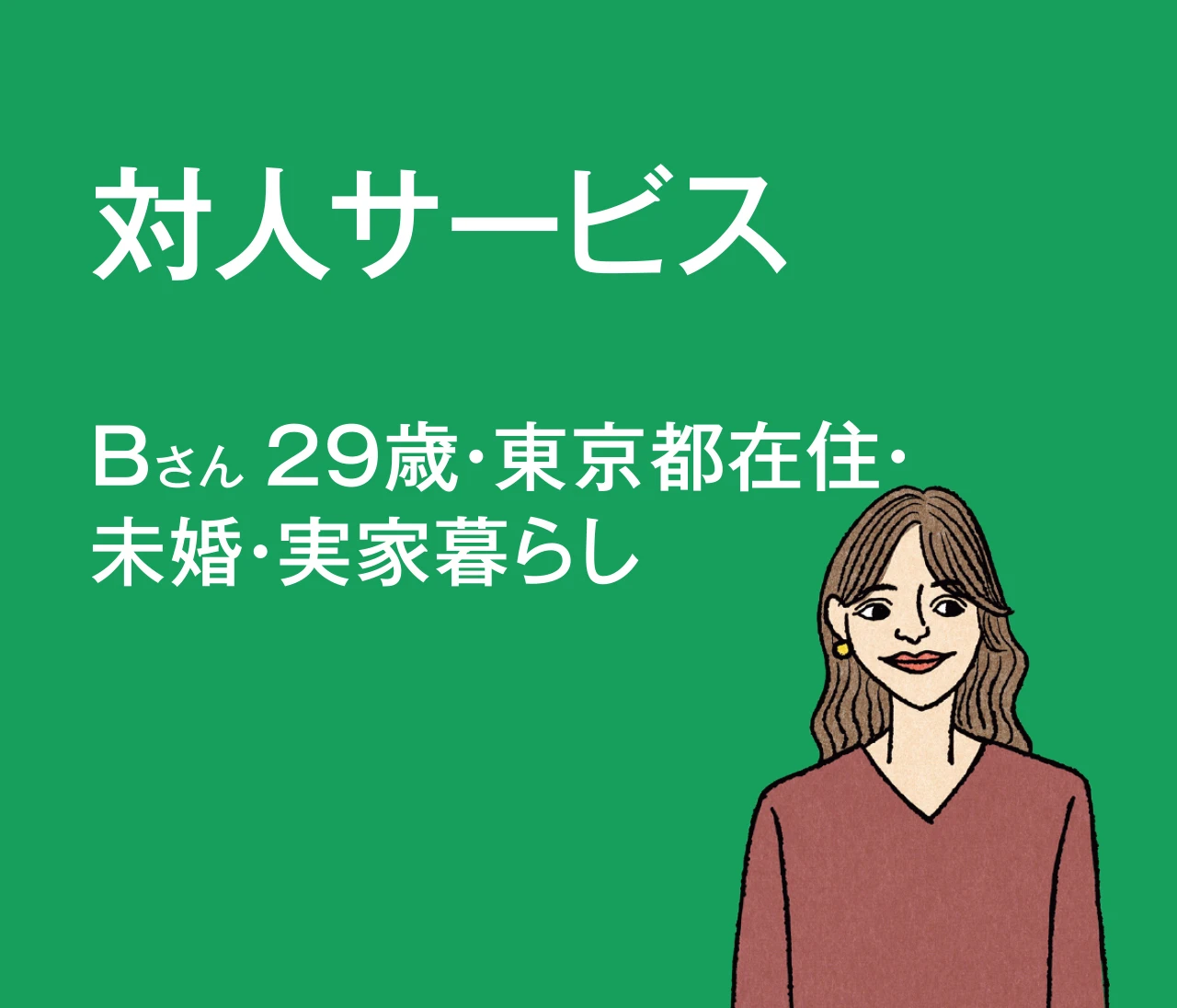




 Baila Channel
Baila Channel