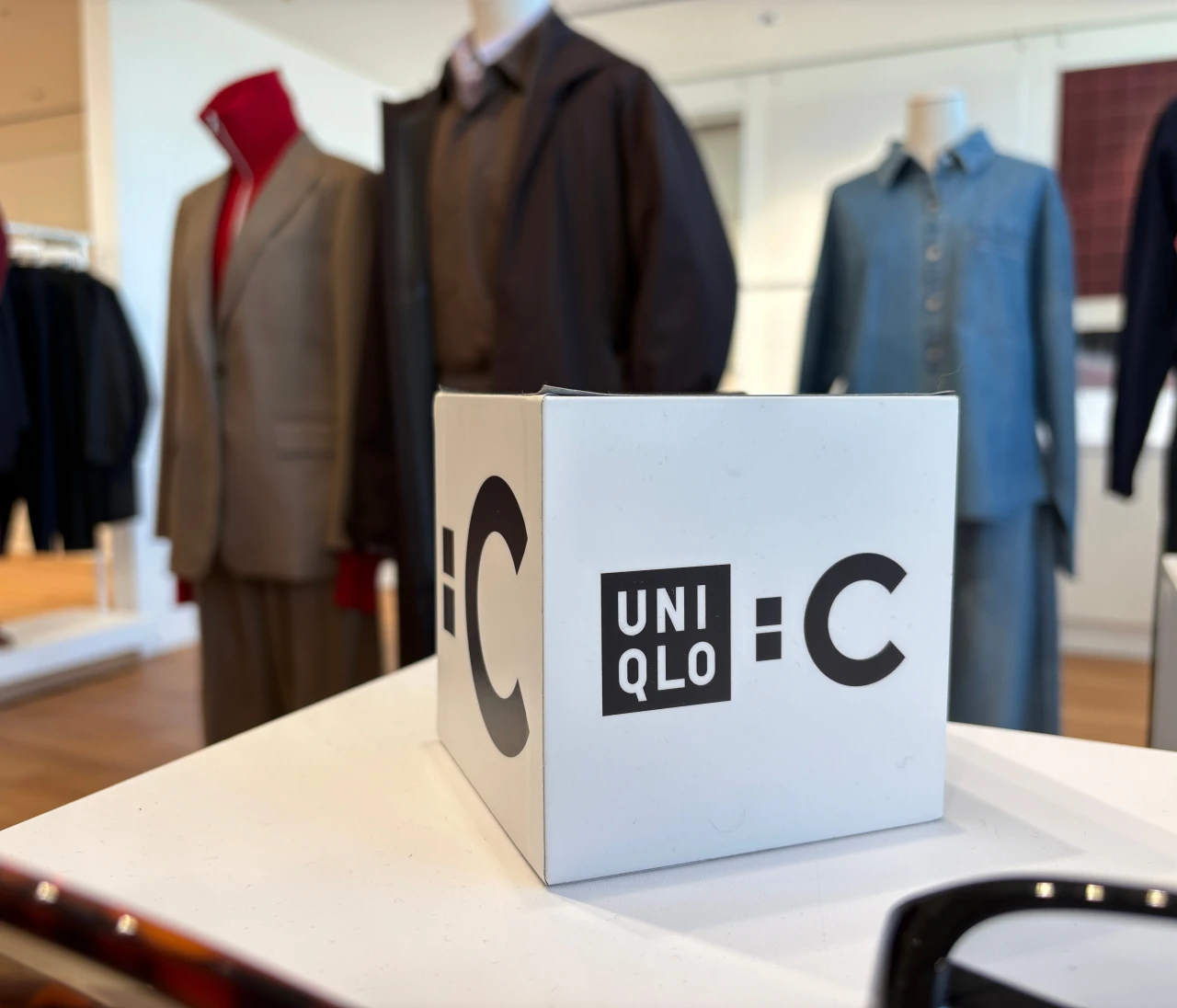「落ちるの一秒、ハマると一生」と言われる歌舞伎沼。その深淵をのぞき、沼への入り方を指南するこの連載。今月ご紹介するのは、俳優として舞台に立ちながら立師として活躍する山崎咲十郎さんと尾上菊次さんです。立師とは歌舞伎独特のアクション、立廻りを考えて実際に演じる俳優へ付けるお仕事。現在、歌舞伎座で上演中の『極付印度伝 マハーバーラタ戦記』も二人が立廻りを作っています。今回は、そんな二人の稽古場にバイラ歌舞伎部が潜入!! どんなふうにして、歌舞伎の立廻りはできていくのか、たっぷりお話を聞きました!

↑(左)山崎咲十郎●やまざきさくじゅうろう 1975年生まれ。河原崎権十郎一門。1992年十七代目市村羽左衛門に入門し初舞台を踏む。
(右)尾上菊次●おのえきくじ 1986年生まれ。尾上菊五郎一門。2004年国立劇場第17期歌舞伎俳優研修修了。
二人とも、菊五郎劇団の立廻りで活躍。立師を勤める。最近では咲十郎、菊次、中村獅一の三人で『新作歌舞伎 ファイナルファンタジーX』の立師を勤めた。

↑刀を構えると、とたんに精悍な表情になる二人。着物での立廻りは、やっぱり特別かっこいい♪
■インドの神話が歌舞伎に。武器にはモーニングスターも!?
まんぼう部長 今日は、歌舞伎俳優であり、立師の山崎咲十郎さんと尾上菊次さんの登場です。11月歌舞伎座で上演中の『極付印度伝 マハーバーラタ戦記』の立廻りを作っているところにお邪魔しました!
ばったり小僧 普段は見られないところを拝見できて感動です! 迫力があってかっこよかったですね~♪ 「立廻り」というのは、いわゆるアクションのことですよね。
咲十郎 そうですね。映画などでの“殺陣”(タテ)とは違って、歌舞伎の立廻りは、リアルではなくて様式的で、踊りに近いようなものです。その振り、立廻りにおける「手」(動き)を付けるのが、私たち、立師の仕事です。
菊次 古典歌舞伎の場合、立廻りの手はだいたい決まっていますけれど、新作歌舞伎の場合は、一から考えることになります。
部長 今回の『マハーバーラタ戦記』は、6年前に初演された作品の再演で、前回もお二人で立廻りを考えられたとか。インドのお話ということで、やっぱり立廻りにもインドらしさを取り入れたりしたんでしょうか?

↑台本で場面やセリフを確認しながら立廻りを考えていく。ときにはいい案が思い浮かばず、しばらく動きが止まることも。二人で大勢の俳優さんの立廻りを作っていくのは本当に大変です!
咲十郎 はい。まず大きく違うのは、闘うときの武器ですね。たとえば今回は古典の歌舞伎には出てこない「盾」が出てくるので、盾を使う立廻りは、映画なんかを観て研究したり。
また日本の刀は、片刃で曲刀(片側に歯があり、反りがついている)ですけれど、この作品で使う「剣」は、両刃で直刀(両方に刃があり、まっすぐな剣)なので使い方も変わってきます。
菊次 普段の歌舞伎には絶対出てこない「モーニングスター」という武器も出てきます。トゲトゲの球体がこん棒の先についているようなもので、6年前は、色々な資料を見ながら、 「この役には、この武器があっているな」ということで、モーニングスターを選びました。
小僧 あのイガイガの当たるとめっちゃ痛そうな武器ですね!? あんなワイルドなものが歌舞伎の舞台に!?
咲十郎 新作を作るときは、とにかく色々な映像を参考にします。映画『トロイ』でギリシャ系の戦士の戦い方を研究したりして、使えるところは使おうと……と言いつつ、実際に使える手はなかなかないのですけれどね(笑)。

↑立廻りの流れ的に「ここらへんで、ちょっと座りたいんだよね」と膝をつく咲十郎さんに合わせて、菊次さんもこのポーズ。決まった~!!
部長 今回の舞台は、前回の立廻りとは、また違うものになるんですか?
咲十郎 そうですね。まず、その役をなさる方によって変わってくるというのがあります。たとえば、先ほど考えていたのは、(尾上)菊之助さんと(中村)萬太郎さんが闘う場面の立廻りだったのですが、前回の舞台では、菊之助さんと(坂東)亀蔵さんがなさっていました。そのときの映像を見ると、多少、二人で自分たちが動きやすいように変えていたりする部分もあるのです。稽古着で動くのと、鎧を着て動くのでは勝手が違うという事がありました。
それをあらためて再現した時に「この動きより、こっちのほうが動きやすいかも」というところがあれば、もう一回、整理して、今度なさる方々にお渡しするという感じです。
菊次 大勢出てくるシーンは、人数が変われば動きや配置も変わってきますし、前回の映像を見て「ちょっと変えたいね」という部分も出てきたので、そこを新たに考えたりしました。

↑「自分たちの考えた立廻りが、だんだん形になっていくのが楽しい」と咲十郎さん。「でも見るたびに、ここはもっとこうしたほうがいいと気づくことがあるので、どんどん改善が必要になるんですね」。立師の仕事には終わりがない!!
■立廻りの型には、全部名前がついている
部長 そういえば、先ほどトランプを使って、二人で何か相談していらっしゃいましたけれど、あれは何をしていたんですか?
咲十郎 大きい「盾」を持っている人の動きを考えていたのです。大人数の立廻りを考えるときは、混乱しないように道具を使うこともあります。ペットボトルを並べるときもあれば、色の違う毛糸を使うときもあるし、何でも使いますね。
部長 考えた立廻りを俳優さんに伝えるのも大変そうですね。
咲十郎 立廻りの型には、ひとつひとつ、名前がついています。基本的なところだと、二人が向かい合って、山を書くように刀を振り下ろす「相山形」、相手の刃を払うことは「払い落とし」、立ち位置を入れ替わる「入れ替わり」……など細かく名称がついていて、これを組み合わせて立廻りは作られます。
ですので、俳優さんにお伝えするときも、たとえば、「相山形、入れ替わって、頭払い、天(二人が頭上で刀を合わせる)、地(下の方で刃を合わせる)、まわして跳ね上げる」などと、順番に言葉で説明してお伝えします。
菊次 私たちが実際にやってみせたり、複雑でわかりにくいときは、映像に撮ってお渡しするときもありますね。
部長 立廻りの型の名前は、全部で何種類くらいあるんですか?

↑「普段はトランプは使わないんですけれど」と言いつつ、盾を持っている人の動きをトランプで再現する咲十郎さん。大人数の立廻りは、わかりやすいように道具で確認するそう。ちなみに「トランプは昨日コンビニで買いました(笑)」。
咲十郎 どうでしょう。3ケタはいくかもしれないですね。まあ、それを全部言える人はいないと思いますけれど。
小僧 しぇ~~~、そんなに!?
菊次 忘れないように、作っている途中で台本に順番を書き込むようにしています。でも、書き込み方に決まりはなくて、人それぞれなので、他の人の書いたものを見ても全然わからなかったりするんですけれど(笑)。
部長 立廻りを作っていく過程を拝見していたら、音楽との兼ね合い、連携がすごく大事なんだろうなと感じました。
咲十郎 そうですね。たとえば三味線の合方(曲)で、「テレンツトン」で始まって、「ツンシャンシャン」で終わる、この幅を「一杯」と言うんですが、古典の立廻りだったら、主役の方と「今回、何杯くらいで行きましょうか」「五杯でやろうか」などと相談して、その尺の中で作ったりします。
小僧 その時間の幅は、もう体に刻み込まれているんですね。
咲十郎 作るときから、口三味線に合わせて作っていく感じです。一方、新作の場合は逆のところもあって。今回は、音楽は棚川寛子さんという舞台音楽家の方が担当されているんですけれど、「ここの立廻りにこんな音が欲しいです」とか、「ここでこの役の立廻りがあるので、音楽で盛り上げて欲しいです」とお願いしたりもします。

↑立廻りが完成すると、忘れないように順番などを台本に書きこむ菊次さん。一方、咲十郎さんは、タブレット端末派。これで前回の舞台の映像もしばしばチェックしていました。
部長 そうすると、稽古場では音楽を作りつつ、立廻りを作って……といろんなことが同時進行で行われていくんですね。
菊次 初日が開いてからも作り続けているとも言えますね(笑)。実際、やってみて動きが間に合わないとか、もっと華やかに見えたほうがいいとか。ここがちょっと間延びするから、テンポを縮めようとか。徐々に細かく修正されていって、千穐楽まで変化していくこともあります。
咲十郎 だから毎回、立廻りはチェックします。揚幕から見たり、たまに客席にいって、お客様の反応を見たり。皆様がウワーッと喜んでくださっているのを見ると、すごく嬉しいし、立師としてやりがいを感じます。
部長 華やかな立廻りは、歌舞伎のクライマックスシーンには欠かせない大切な演出ですよね。
菊次 はい。正義と悪が最後に対決する場面だったりするので、それがないと終われないという大事なもの。やっぱり客席を盛り上げられるような立廻りが理想です。
咲十郎 役柄の性根がそこで一気にガーっと出るのも立廻りの面白さ。それぞれの役に合った立廻りを大事にしたいと思っています。

↑写真撮影の途中、思わず笑顔がこぼれる二人。阿吽の呼吸で作られていく立廻りだけに、咲十郎さんと菊次さんの息もぴったり。お互いに信頼しあっているのがよくわかります♪
■立廻りにも守るべき伝統がある!!
小僧 「立師」というのは、何か資格があるとかではないんですよね。俳優として、演技をしている中で、自然と身につけていったものなんですか?
咲十郎 そうですね。お芝居をする中で、先輩の方々に色々と動きを教わって、さらに立師の方のお手伝いや助手をする中で、いろんなことを吸収していくという感じです。そのうち、どこかのタイミングで、座頭や主役の方が「今度の芝居の立廻りをやってみなさい」と指名して下さり、立師をさせていただくというパターンが多いと思います。
部長 立廻りを作るときに、大事にしているのはどんなことですか?
咲十郎 先輩から教わったことから外れないように、間違ったことをしないように、ということです。新作のときも、「これをやったら先輩から怒られないかな」というのは常に頭にありますね。
菊次 とくに私たちは、「菊五郎劇団」(六代目尾上菊五郎の亡きあと、薫陶を受けた役者を中心に結成された劇団)の人間で、菊五郎劇団は立廻りを大事にしてきた劇団としてのプライドがあります。だから約束事はきちっと守りたい、劇団の人間として恥ずかしくないようにしたいという思いが強いんだと思います。

↑「歌舞伎の舞台って、意外ときついんです。衣裳は重いし、動きも激しくて、足腰にくるんですよ」と咲十郎さん。「舞台で正座から立ち上がるようなときに、どっこいしょとならないように、サッと勢いよく立てるようにしたいので、スクワットなどで下半身を鍛えています」。
咲十郎 菊五郎劇団には、立廻りの大先輩である坂東八重之助さんという方がいらっしゃいます。古くを辿ると私の兄弟子にあたる方で、そこから代々受け継がれているものを後輩に伝えていくことが、歌舞伎の伝統を守ることになるのではないかと思います。
菊次 咲十郎さんはアイディアがすごくて、最初はたぶんびっくりするようなところまで考えていると思います。そこから「これはできる」「ここまでやったらマズいな」って選別していると思うんですけれど、僕はその最初の段階に考えていることを知りたいですね。咲十郎さんの頭の中を見たい(笑)。
小僧 その守るべきラインって、私たち素人が見てもわからないものですか?
菊次 わからないと思います。はっきりとあるものではなく、立師の意識や心構えなので。
部長 まさにプロフェッショナルの領域なんですね。すごいですねぇ。そして新しいものを作り上げる発想力、素晴らしいです!

↑立師はやっぱり体が資本! 「日々のケアが大事ですね」と菊次さん。
咲十郎 発想力も必要ですけれど、立師には、“芝居勘 ”みたいなものが大事かなと思います。さっき二人でやっていて、「こっちにはいけない」と立ち止まっちゃうときがありましたけれど、その「いけない」感じがわからないとダメですね。どっちでも行けちゃう人もいますが、「いけない」という基本の芝居勘は大事です。立廻りも踊りも基本の足運びなどがわかっていないと、きちんとした動きの並べ方はできないと思うので。
それから役者によって好きな型というのも結構あるので、普段から見ていて、「この人はこういう型が好きなんだな」と覚えておいて、気持ちよくやっていただける型をつけることも大事です。なので、立廻りだけでなく、普段の舞台を見ることも大事です。
小僧 皆さん、好きな型、似合う型があるんですね。
菊次 ありますね。たとえば若旦那(菊之助さん)だったら、「柳」という型(刀を頭上で横向きに構えて見上げる形)がきれいでお似合いなので、立廻りの手に入れることが多いです。

↑動きに無駄がなくて、ストイックな雰囲気の咲十郎さん。おっとりしたやわらかい感じの菊次さん。素敵な二人を前に、小僧はいつになくもじもじ★
部長 なるほど。歌舞伎は総合芸術と言いますけれど、立師のお仕事も作品に大きく影響していることがよくわかりました! では、最後に今月の舞台について、読者へのメッセージをお願いいたします!!
咲十郎 今回、歌舞伎座で両花道なんですよ。これは久しぶりのことです。しかも花道で、役者たちが結構派手に動くので、ぜひ観ていただきたいですね。
菊次 仮花道のほうは、通常の花道より、俳優さんを近くで観られるので、前回も歓声がたくさんあがっていたのを覚えています。ぜひ間近で、立廻りの迫力を楽しんでください!
部長 わあ、それは楽しみ。もちろんお二人も舞台に登場するんですよね!
小僧 みんなで目を皿のようにして、お二人を探しちゃいます~!!

↑「『マハーバーラタ戦記』は、インドが舞台の新作で、音楽も衣裳も斬新。 言葉もわかりやすいので、歌舞伎初心者の方も観やすいはずです。ぜひご覧ください」と咲十郎さんと菊次さん。二人が作り上げた立廻りが舞台でどんなふうに展開されるのか、楽しみでっす!!

■歌舞伎座新開場十周年
「吉例顔見世大歌舞伎」
期間: 2023年11月2日(木)~25日(土)
劇場:歌舞伎座
【休演】10日(金)、20日(月)
<昼の部> 午前11時~
極付印度伝
『マハーバーラタ戦記』(まはーばーらたせんき)
青木 豪 脚本
宮城 聰 演出
序幕 神々の場所より
大詰 戦場まで
出演
迦楼奈(かるな) / シヴァ神(しん):尾上菊之助
太陽神(たいようしん):坂東彌十郎
仙人久理修那(せんにんくりしゅな):中村錦之助
帝釈天(たいしゃくてん):坂東彦三郎
百合守良王子(ゆりしゅらおうじ):坂東亀蔵
風韋摩王子(びーまおうじ):中村萬太郎
汲手姫(くんてぃひめ):中村米吉
阿龍樹雷王子(あるじゅらおうじ) / 梵天(ぼんてん):中村隼人
納倉王子(なくらおうじ):中村鷹之資
我斗風鬼写(がとうきちゃ) / ガネーシャ:尾上丑之助
鶴妖朶王女(づるようだおうじょ) / ラクシュミー:中村芝のぶ
沙羽出葉王子(さはでばおうじ):上村吉太朗
森鬼獏(しきんば):尾上菊市郎
森鬼飛(しきんび):上村吉弥
道不奢早無王子(どうふしゃさなおうじ):市川猿弥
亜照楽多(あでぃらた):河原崎権十郎
羅陀(らーだー):市村萬次郎
多聞天(たもんてん):市川團蔵
大黒天(だいこくてん):坂東楽善
那羅延天(ならえんてん):尾上菊五郎
<夜の部> 午後4時30分~
一、
秀山十種の内
『松浦の太鼓』(まつうらのたいこ)
両国橋の場
松浦邸の場
同 玄関先の場
出演
松浦鎮信:片岡仁左衛門
大高源吾:尾上松緑
近習鵜飼左司馬:市川猿弥
同 江川文太夫:中村隼人
同 渕部市右衛門:中村鷹之資
同 里見幾之丞:中村吉之丞
同 早瀬近吾:市村橘太郎
門番平内:片岡松之助
お縫:中村米吉
宝井其角:中村歌六
二、
『鎌倉三代記』(かまくらさんだいき)
絹川村閑居の場
出演
三浦之助義村:中村時蔵
時姫:中村梅枝
おくる:市川高麗蔵
阿波の局:中村歌女之丞
讃岐の局:中村梅花
富田六郎:中村松江
母長門:中村東蔵
佐々木高綱:中村芝翫
三、
『顔見世季花姿繪』(かおみせづきはなのすがたえ)
春調娘七種
三社祭
教草吉原雀
出演
〈春調娘七種〉
曽我五郎:中村種之助
静御前:尾上左近
曽我十郎:市川染五郎
〈三社祭〉
悪玉:坂東巳之助
善玉:尾上右近
〈教草吉原雀〉
鳥売りの男実は雀の精:中村又五郎
鳥刺し実は鷹狩の侍:中村歌昇
鳥売りの女実は雀の精:片岡孝太郎

取材・構成/バイラ歌舞伎部 写真/山下みどり
まんぼう部長……ある日突然、歌舞伎沼に落ちたバイラ歌舞伎部部長。遅咲きゆえ猛スピードで沸点に達し、熱量高く歌舞伎を語る。
ばったり小僧……歌舞伎歴2年。やる気はあるが知識は乏しい新入部員。若いイケメン俳優だけでなく、オーバー40歳の熟年俳優も大好き。















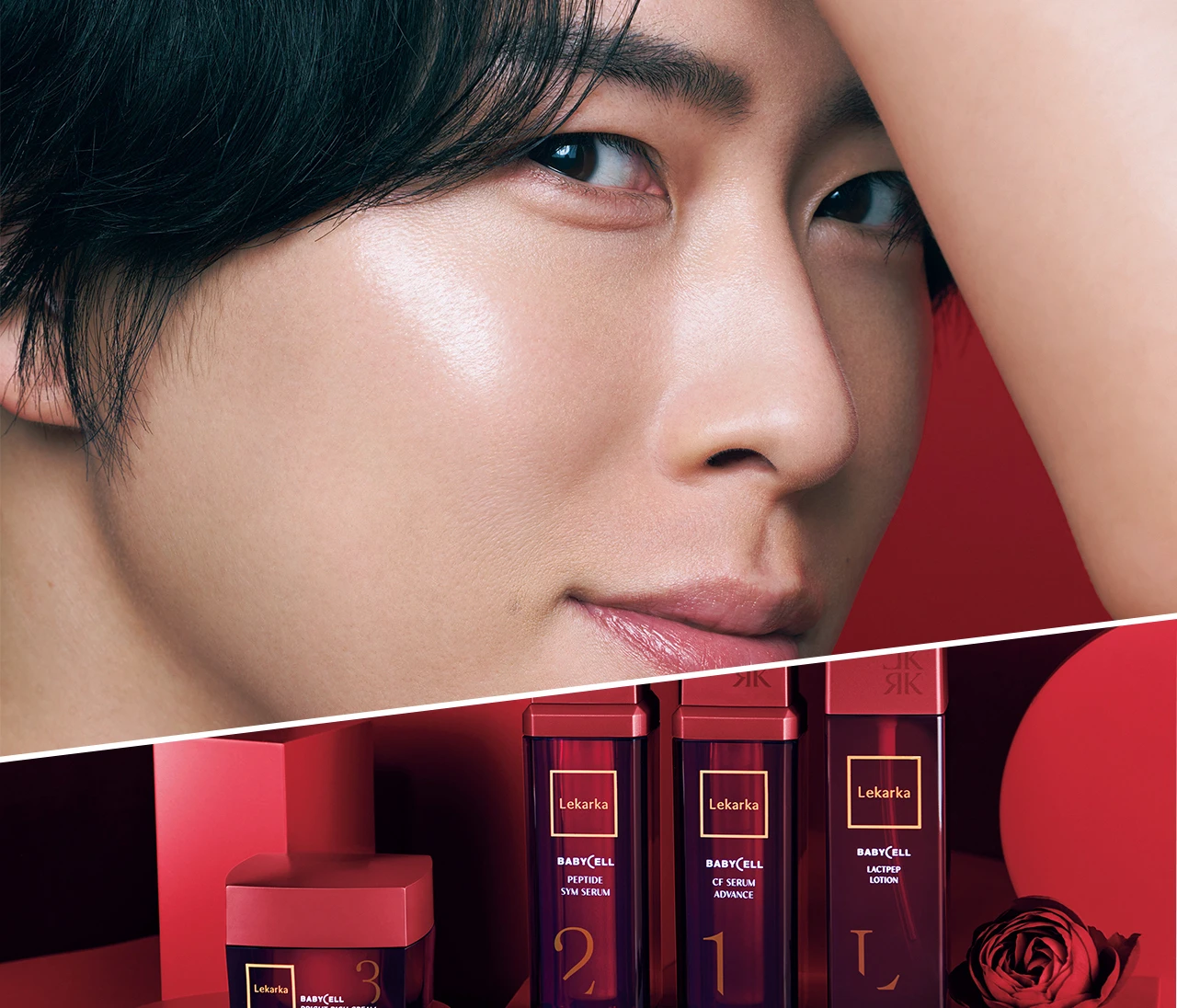










 Baila Channel
Baila Channel