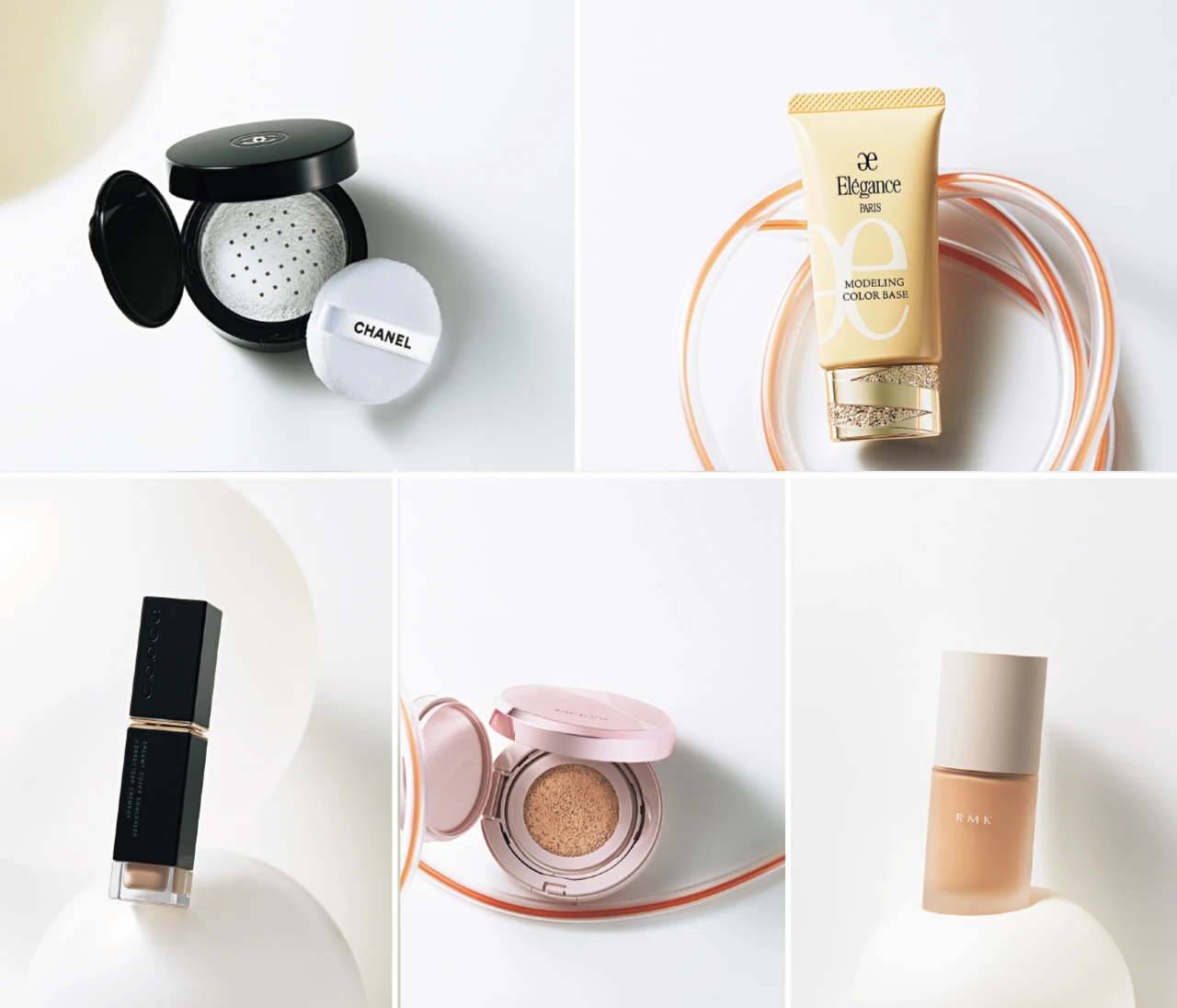出版の仕事に関わる人は、どんな視点から本を選び、読んでいる? 今回は翻訳家の柴田元幸さんに、「自分にとってスペシャルな本」を教えてもらった。

翻訳家
柴田元幸先生
しばた もとゆき●アメリカ文学研究者・翻訳家・編集者。東京大学名誉教授。1980年代から翻訳を始め、20世紀半ば以降のポストモダン文学が専門分野になる。

(柴田さんが手がけた本)
『ムーン・パレス』
ポール・オースター著 柴田元幸訳
新潮文庫 990円
NY在住の小説家で詩人、ポール・オースターの初期代表作。初の翻訳出版は1994年と、30年近く前になるも、今でも読み継がれている!
【翻訳家】が読む本

(とっておきの本)
左から
『A Kayak Full of Ghosts: Eskimo Folk Tales』
Lawrence Millman著 Interlink Books
$13.95
『アメリカの鱒釣り』
リチャード・ブローティガン著 藤本和子訳
新潮文庫 649円
『おそ松くん』
赤塚不二夫著
竹書房文庫 全22巻 各660円
現代アメリカ文学を中心に、英語圏の作品を翻訳し、世に送り出している柴田さん。幼少期に親しんだのは、意外にも(?)、赤塚不二夫のギャグ漫画。
意味のない笑いがもたらしたもの
「僕が翻訳をするときに意識するのは、原文が持つユーモアや勢い、リズムを生かすこと。中でもユーモアは、最も損なわれやすいものだから、いちばん大事にしたい……と言い切れるかもしれません。そして笑いを知った作品といえば、どうしたって『おそ松くん』なんです。子どもの頃に連載を読んでいましたが、ほかの漫画みたいにシリアスじゃないし、ギャグも乱暴。その上で極端に優しい部分もあって。最高でした。うちの親なんかは娯楽の中にもメッセージ性を求めていましたが、『おそ松くん』を読んで、意味なく笑えるのもいいことだよなと感じましたね。好きなキャラクターは、頭に旗を立てたハタ坊。彼の、どうも周りの空気を読まないというか、いきなり突拍子もない行動をしちゃうところに、ずっと親しみを持っている気がします。アメリカの作家、O・ヘンリーの短編を下敷きにした話もあるんですよ。もちろん、大人になってから気づいたことなんですが。赤塚不二夫しかり、O・ヘンリーしかり。笑いやペーソス、センチメンタリズムが根底に流れる作品には、惹かれるものがあります」
藤本和子さんの訳で、新たなる翻訳の魅力を知った
ナンセンスさが魅力の連作短編集『アメリカの鱒釣り』は、柴田さんが訳文の素晴らしさに圧倒された一冊。
「原文から醸し出される不思議な感覚が、そのまま伝わってくる。音楽でいうなら、録音でなくライブの熱量そのままの日本語訳です。これを1970年代に試みた藤本和子さんは素晴らしいし、読んで衝撃を受けました。当時、僕が知っていた翻訳書の多くは、ひととおりの意味がわかればよく、原文の雰囲気や文体などは期待できないのが前提でしたから。これは“現代文学の翻訳の流れを変えた人”、“言い出しっぺ”的なパワーに触れられる本。学生にブローティガンを読ませると『どこが新しいのかわからない』という意見も出るんですが、それだけ藤本さんのスタイルが定着した証拠ですよね。僕や、現代の翻訳者たちは、藤本チルドレンですから。作者のブローティガンは、強さが美徳とされがちなアメリカ社会のノリになじめなかった男性。彼が紡ぎ出す不条理や笑いの感覚は、現代を生きる人が読んだほうが逆にリアルかもしれませんね。アメリカ文学は、スコット・フィッツジェラルドの『グレート・ギャツビー』みたいに、栄光への挫折をすくい取る作品も多いですが、一方でヘミングウェイみたいに強さへの美学を貫く作家もいる。はみ出し者のブローティガンと向き合い、マッチョなものに冷や水を浴びせた藤本さんの視点の鋭さと、少数派への共感も感じます」
そして柴田さん自身、今もなお、新たな分野の翻訳に挑戦し続けている。
「このところ、女性作家の作品を発掘し、翻訳する機会が多いんですよ。裏返せば、それだけ無視されてきた流れがあるからです。発表後、評論もされないまま本人は亡くなり、重要なテキストの真意がわからない作品もありますね。これに関しては、僕にも、もったいないことをしてきたという反省があって。長い間、英語圏に住む白人男性の翻訳や研究が自分の担当で、女性の文学は女性が進めたほうがいいと、勝手に思い込んでいた部分があります。分業みたいな感覚だったでしょうか。もちろんそんなこと、誰からも決められていなかったんですけれどね」
私たちがもつ「お話」の定義を覆してくれるイヌイットの民話
また最近、読んで圧倒されたのが、カナダ北部やグリーンランドなど氷雪地帯で暮らす先住民族・イヌイットの民話を聞き書きし、まとめた短編集『幽霊でいっぱいのカヤック』だとか。今回はその中から、バイラ読者のために自身の訳を一編、紹介してくれた。
「もしかしたらこの『鯨の女房』は、我々が知っているお話のかたちとは違うなと、感じられるかもしれません。“起承転結”みたいなストーリーへの固定観念や、物事への常識や考え方が覆されるというか。『幽霊でいっぱいのカヤック』の中には、こんな感じで短いエピソードが119も収められています。我々がなじみ深い勧善懲悪的な話もあるものの、やっぱり、少数ですね。集団の中でのルール、性への捉え方なども、僕が読んできた物語とは違いました。予想外の結末に連れていってくれる感覚が、この短編集にはあります」
原著者のローレンス・ミルマンは、キノコなど菌類の研究者で、北極圏などを旅する探検家。
「前書きを読むと、ミルマンさんは友人を介してイヌイットのコミュニティに入る機会があり、民話を聞かされ衝撃を受けて、採取を始めたとのこと。話を誰から、どのように聞いたかも記されています。今は消えつつある物語を文字で書き留めている、という点でも興味深いです。
もちろん、型にはまった物語も、新しい装いで読ませてもらえれば、悪くないです。ただ形式にしばられない楽しさというかね。“当たり前”以外の何かに触れるのも、いい読書体験ではないでしょうか」
「鯨の女房」 翻訳 柴田元幸
昔、イリツィナという女がムール貝を獲りに海岸に出ていった。とても美しい女で、多くの男に好かれていた。海岸に立っていると、鯨も彼女を好きになり、自分のものにした。こうしてイリツィナは鯨と夫婦になって海の底で暮らすようになった。鯨の方が強いので、文句も言えない。でも実は、彼女も鯨との暮らしを気に入っていた。鯨がカヤック乗りと女房を交換すると、イリツィナは全然喜ばなかった。「もっと! もっと!」と彼女は叫んだ。カヤック乗りは彼女を鯨に返し、以後二度と、どの鯨とも女房を交換しなかった。鯨がセイウチ、ジャコウウシ、アゴヒゲアザラシと女房を交換しても同じことが起きた。イリツィナは死ぬまで鯨と一緒に暮らし、死ぬとずっと昔にムール貝を獲っていたまさにあの海岸に打ち上げられた。誰も彼女だとはわからなかった。もうずっと前に、鯨の姿になっていたからだ。彼女の肉と脂肪で、人々はまるひと冬食いつなぐことができた。
――ローレンス・ミルマン採録『幽霊でいっぱいのカヤック』(2010)より
© Lawrence Millman, 2004
こちらもチェック!
柴田元幸責任編集
『MONKEY vol.28 特集 老い』
柴田さんが責任編集を務める文芸誌。10月15日発売の最新号は老いをテーマに様々な物語を紹介する。今回触れた、イヌイットの民話も7本訳出し、掲載。
撮影/kimyonduck イラスト/naohiga 取材・原文/石井絵里 ※BAILA2022年11月号掲載





















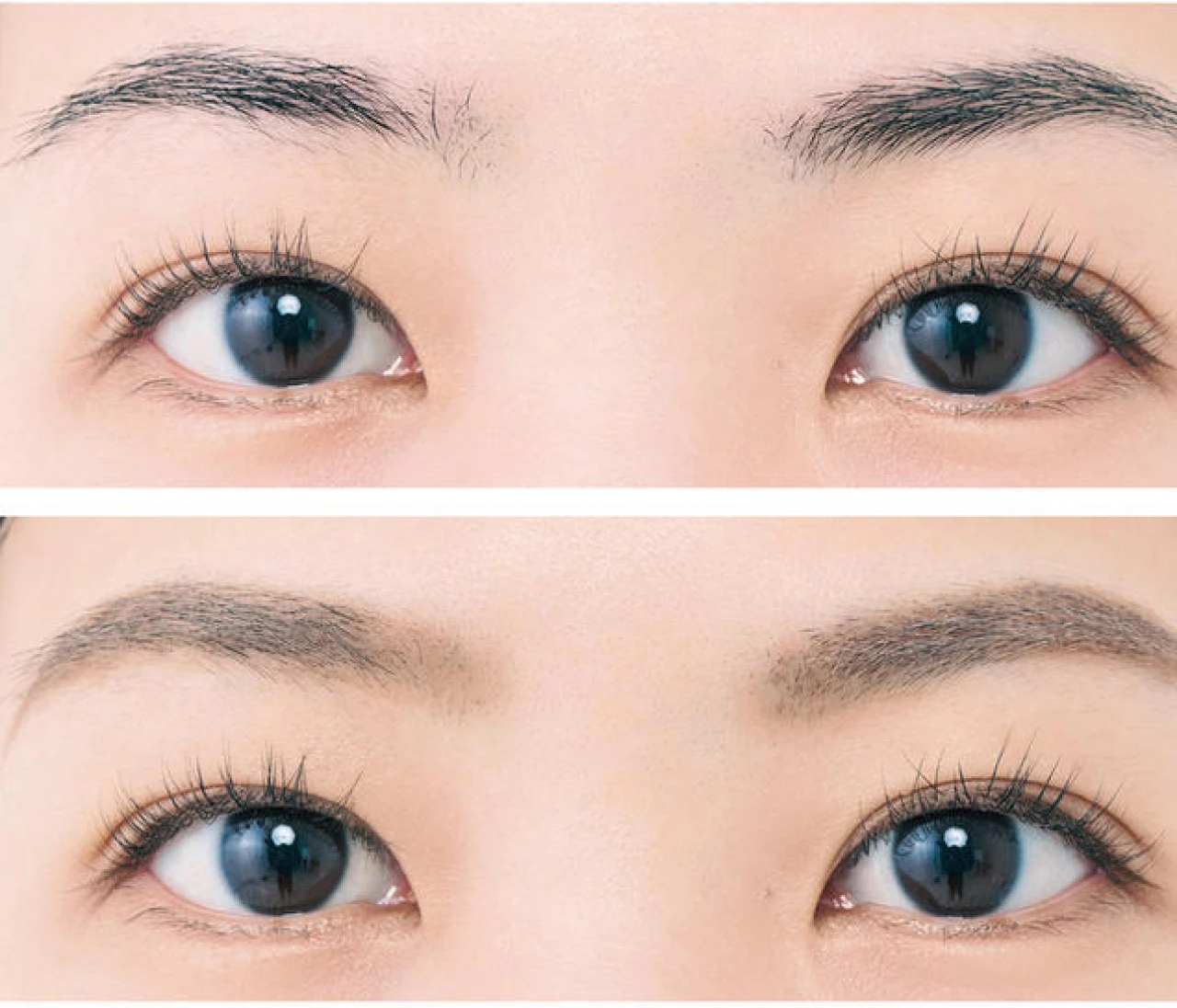
 Baila Channel
Baila Channel




![大人の肌見せはデコルテ&ウエストをのぞかせる「バタフライシルエット」でかっこよく![ヘアアレンジ付き]](https://img-baila.hpplus.jp/image/b4/b4780bfc-9f41-4f6e-8046-09244547f914-1280x1096.jpg)