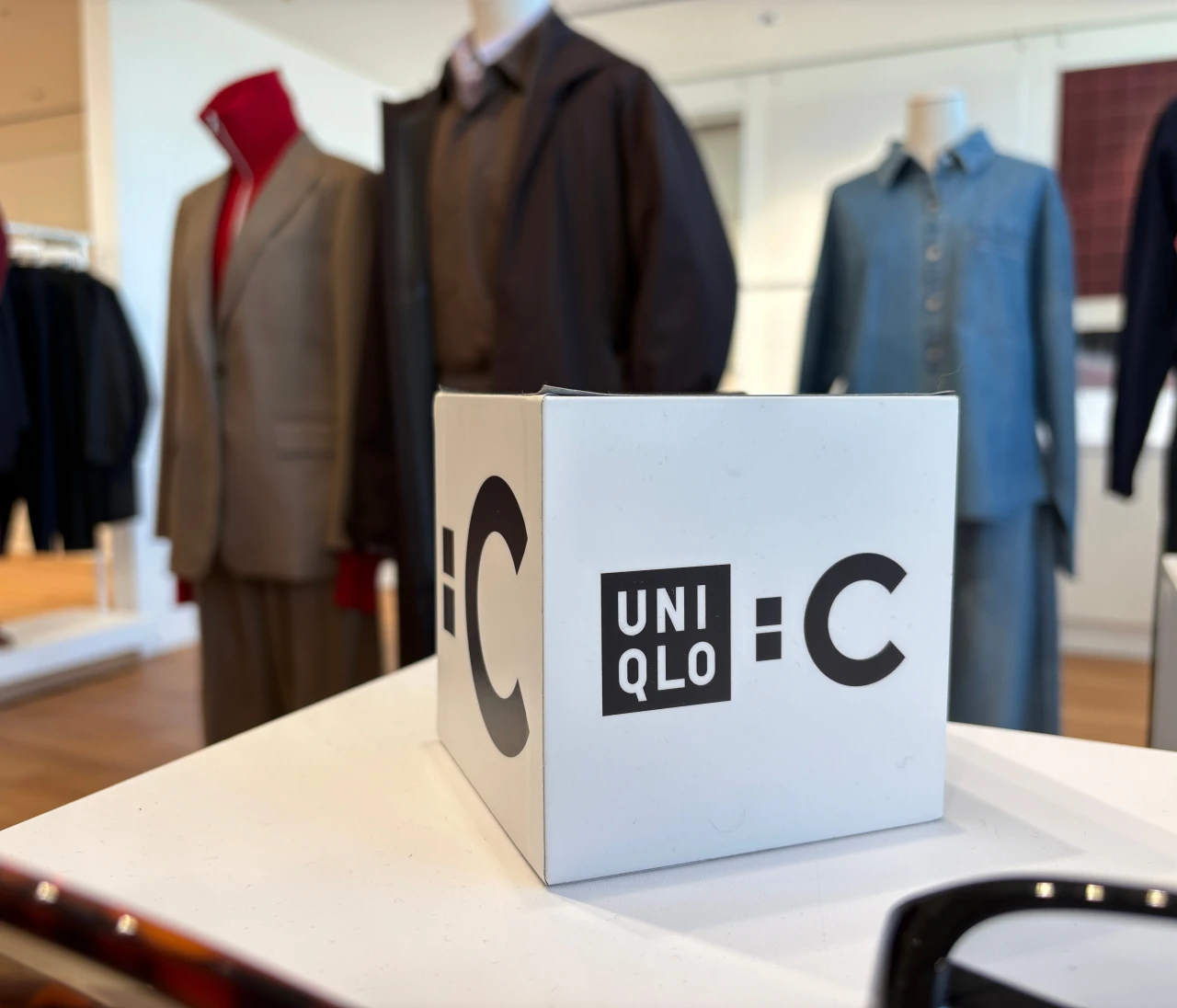2025年は戦後80年、国連創設から80年という節目。国連で軍縮部門のトップを務める中満泉さんと大江麻理子さんが対談。国際秩序を回復し平和のために国連が果たす役割、日本ができることを伺いました。

第一線で軍縮に取り組まれている中満さんに平和についてや人生のことを伺います
――大江麻理子さん
“軍拡競争は誰のためにもならない”と働きかけていくことが日本の役割だと思います
――中満泉さん
中満泉さん×大江麻理子さん 対談
国連の軍縮部門にて安全保障や軍縮に関する加盟国の交渉をサポート

様々異なるポジションの中にどんな共通項があるかを探し出しています
――中満泉さん
大江 中満さんは今、国連でどんなお仕事をなさっているのですか。
中満 私が担当している部門は軍縮です。日本でいうと核兵器の問題がすぐ思い浮かぶと思いますが、それだけではなくて、ほかにも大量破壊兵器の化学兵器や生物兵器など色々な恐ろしい兵器があります。それらを禁止する条約があるのですが、その実施をいかに進めていくのか。加盟国同士で交渉しながら約束事をつくっていくわけですが、そのようなプロセスのサポートをしています。また、実際に紛争が続いている現場で使われている通常兵器や小型兵器を制限するための支援も行っています。近年、新しく取り組んでいるのは新興テクノロジーの問題です。サイバー安全保障のプロセスやAIの兵器化に対する規範づくり、宇宙での軍拡防止までその範囲は幅広いです。
大江 具体的にどのようなサポートをするのでしょう。
中満 加盟国同士の議論のサポートをするのですが、会議運営の支援というより、むしろどんな方法で歩み寄れるのかというオプションを提示したり、今のような分断の構図のなかでは加盟国同士で直接議論ができない場面があるので、国連を通じてメッセージの橋渡しをしたりすることもあります。様々異なるポジションの中にどのような共通項があるのかを探し出して、“もしかするとこういう形で妥協すれば合意できるのではないか”ということを私たちのほうで判断してサポートしています。
大江 落としどころを見つけることは、第三者的な立場の方でないと難しいのかもしれませんね。
中満 特に加盟国はやはり自分たちの主張をするのが言ってみれば仕事ですから。一方、私たちはそうではなくて、違いに注目するよりも、むしろ共通項がどのあたりにあるのかをいつも探しているような仕事ですね。ですが今、刻一刻と情勢は悪くなっていき、軍事大国と言われている大きな軍事力を持っている国々はますます自分たちの主張を強固にして、軍縮ではなくて軍拡の方向に進んでるような状況があります。
大江 これだけ各地で紛争が起きていますと、軍縮の議論を進めづらいような気もするのですが。
中満 そのとおりですね。国連での議論も難しいのですが、他方で、軍拡が進みすぎて安全保障環境が悪くなってくると、加盟する国々が“このままいくとまずい、自分たちの安全保障にとってもプラスにならない”とリスクを認識することができます。そこで外交によってそのリスクを軽減し、軍縮によって自分たちの安全保障のプラスになるようにしましょうという共通認識が生まれてくるんですよね。実際に、歴史上で何回かそういうことがありました。たとえば1962年のキューバミサイル危機が挙げられます。米大統領がケネディ、ソ連の第一書記がフルシチョフの時代ですが、おそらく国際社会が全面核戦争にいちばん近づいた瞬間です。それをなんとか解決したあと、共通のリスクを認識することができた米ソ間での直接の交渉によって一年とたたないうちに部分的核実験禁止条約という軍縮条約を締結しました。安全保障は軍事力だけで担保できるものではなく、外交そして軍縮を通じた安全保障も非常に重要であることは、これまでの色々な例からわかると思います。
分断の構図が深まり紛争が続く今、創設80年を迎える国連の役割とは

舞台裏で妥協点を見つけるという形で国連が活躍しているのですね
――大江麻理子さん
大江 ウクライナ侵攻も続いていますし、ガザでの戦闘も停戦までこぎつけましたが先行きは不透明です。
中満 この二つの大きな戦争が及ぼしているインパクトは非常に大きく、中でも緊急の課題は人道状況の改善です。特にガザにおいては、見たことのないひどい人道状況になっています。人口の90%が避難を余儀なくされ、しかも1回ではなく平均で6回、多い人になると19回避難したという報告もあります。今一段階目の停戦ですので、ここから恒久的な停戦、和平プロセスにこぎつけるかが大きな課題です。ウクライナに関しても、これは間違いなく侵攻ですし、国連憲章にも違反しているということで、明らかな国際法違反です。しかも責任を問われない状況が続いているのも問題です。国際法の中核である国連憲章は第二次世界大戦後の国際秩序の根幹ですので、それに対する大きな挑戦で、なんとか私たちは秩序を回復しなければならないと思っています。米科学誌「原子力科学者会報(BAS)」が毎年発表している人類滅亡までに残された時間を象徴的に表す「終末時計」をご存じですか。
大江 はい。滅亡時を午前0時に見立てていて、今年1秒縮まりました。
中満 過去最短の89秒になりました。
大江 これだけ世界の不確実性が高くなっている状況のなかで、国連に求められる役割はどんなことだと考えていらっしゃいますか。
中満 分断の構図が深まり色々なところで紛争が続いている舞台裏で橋渡しをする調停の努力がまずひとつ。目立たない、黒子的な役割ではありますが、加盟国同士の様々な努力を側面から支えていくことが実は冷戦時代の国連のいちばん重要な役割だったんですよね。安全保障、軍縮の分野を中心にお話ししましたが、ほかにもAIなどの新興技術においてのガバナンス、気候変動、拡大する格差、難民問題など色々な課題があります。これだけ難しい問題が山積みですけれども、“世界が協力すれば解決できる”と希望が持てるようなメッセージを常に発信していくことも、困難な時代では重要だと思っています。
大江 今、安全保障理事会が一致点を見いだせず、国連の存在意義が問われることもあります。
中満 そうですね。安全保障理事会がきちんと機能するように改革しなければいけないというのはそのとおりだと思っています。2024年9月に事務総長が未来サミットを招集し、加盟国の交渉によって合意して採択した「未来のための協定」という文書の中でも安保理改革の詳細が盛り込まれています。常任理事国が拒否権を発動することによっていくつかの重要な紛争の解決を不可能にしていることは、安保理の抱える非常に大きな問題点です。同時に、国連が創設された80年前と今日の世界は大きく異なっており、安保理が現代の国際社会の現実やパワーバランスを正確に反映していないということも大きな問題です。21世紀に機能していける国際機関であり続けるためには、安保理改革は避けて通れませんので、私たちにとっても最優先事項です。
大江 日本は国連の常任理事国入りを目指しています。改革の中で現実味を帯びてくることもありますか。
中満 可能性は充分あると思います。日本はそれをどう実現していくかを考え具体的に提示、積極的な外交を展開する必要があり、この数年間が勝負の年と言えそうです。
大江 取材で伺う世界の様々な地域で歓迎を受けるたび、日本の先人たちの努力に感謝することが多いです。色々な国や地域と関係が良好であることも含め、今、日本に期待される役割は国際舞台でも大きいですか。
中満 おっしゃるとおりです。日本に対する信頼はかなり強いものがあって。責任感のある加盟国として日本への期待は大きな強みだと思います。
大江 軍縮ではなく軍拡の方向に進みつつある今、本当に人類は重要な分岐点に立っていると思います。そうしたなかで、軍縮について日本にできることはありますか。
中満 はい。核兵器の問題でいうと、唯一の戦争被爆国ということで、ご存じのように、2024年に日本被団協(日本原水爆被害者団体協議会)がノーベル平和賞を受賞しました。日本で2例目の受賞です。私も授賞式に参列しました。ノルウェー・ノーベル委員会のフリードネス委員長が平和賞に選んだ理由について、「2025年は戦後80年という重要な年であり、その直前に日本被団協にノーベル賞を授与することは、ひとつの大きなモメンタム(機運)をつくるために重要な意味がある」とおっしゃっていました。平和のため、軍縮のために長年活動してきた方々が認められたのです。被爆という日本が持っている、ある意味では非常に特殊で、この上なく悲惨な経験なわけですけれども、その実相を日本としても発信し、立場が分かれて争っている国同士の仲を取り持って、“制限のない軍拡競争というのは誰のためにもならない、どの国にとってもプラスには決してならない”ということをきちんと訴えていくことが、やはり非常に重要な役割ではないかと思っています。

大江麻理子
おおえ まりこ●テレビ東京報道局ニュースセンターキャスター。2001年入社。アナウンサーとして幅広い番組にて活躍後、’13年にニューヨーク支局に赴任。’14年春から『WBS(ワールドビジネスサテライト)』のメインキャスターを務める。

国連事務次長
中満 泉
国際連合事務次長・軍縮担当上級代表。早稲田大学法学部卒業。米国ジョージタウン大学大学院修士課程修了(国際関係論)。1989年に国連に入り、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)に入職。その後、国連平和維持活動局(PKO)政策・評価・訓練部長およびアジア・中東部長、国連開発計画(UNDP)危機対応局長などを経て2017年5月より現職。
撮影/神戸健太郎 ヘア&メイク/YUMBOU〈ilumini.〉 取材・原文/佐久間知子 ※記事の内容は2025年2 月末時点のものです ※BAILA2025年5月号掲載













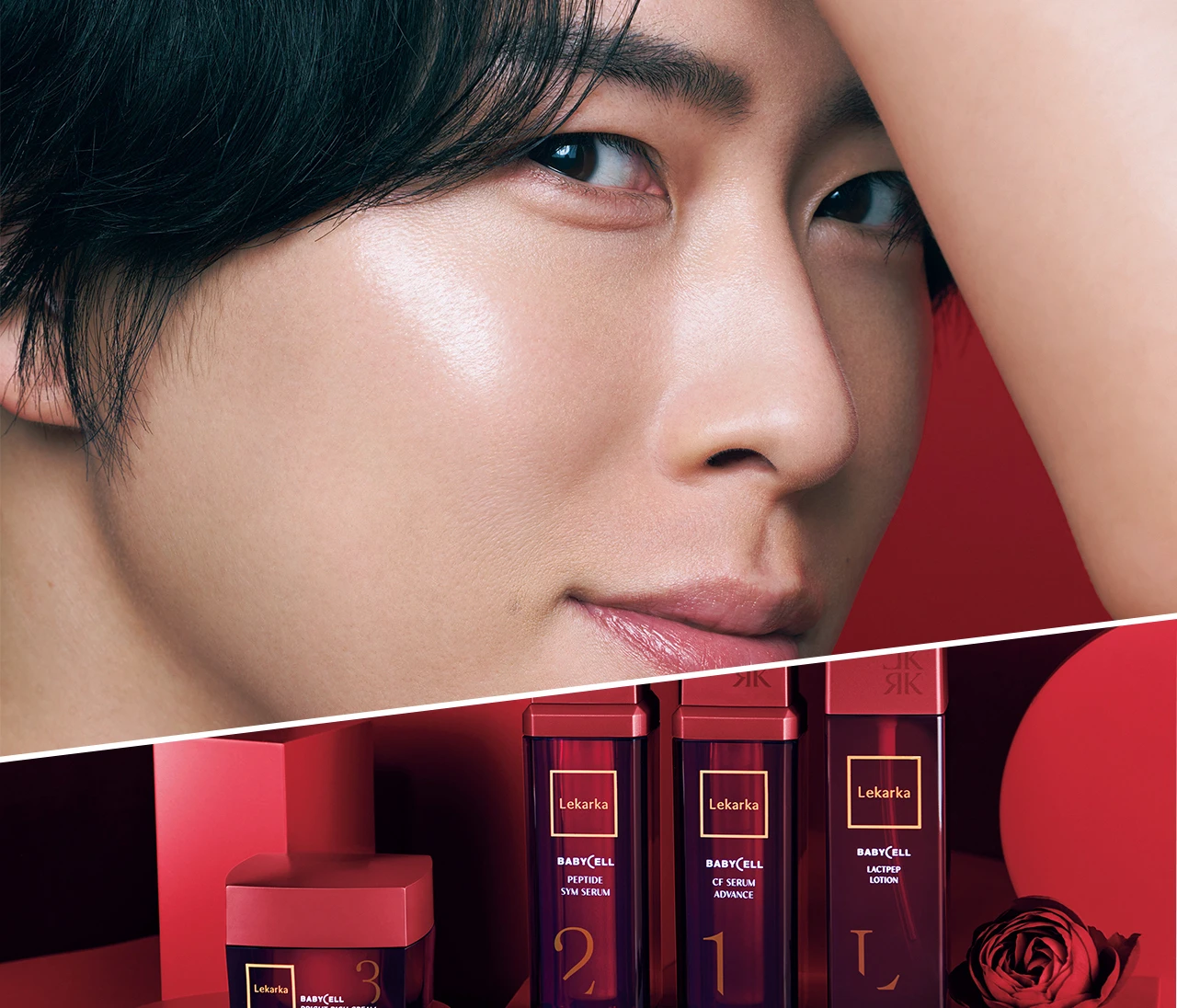












 Baila Channel
Baila Channel