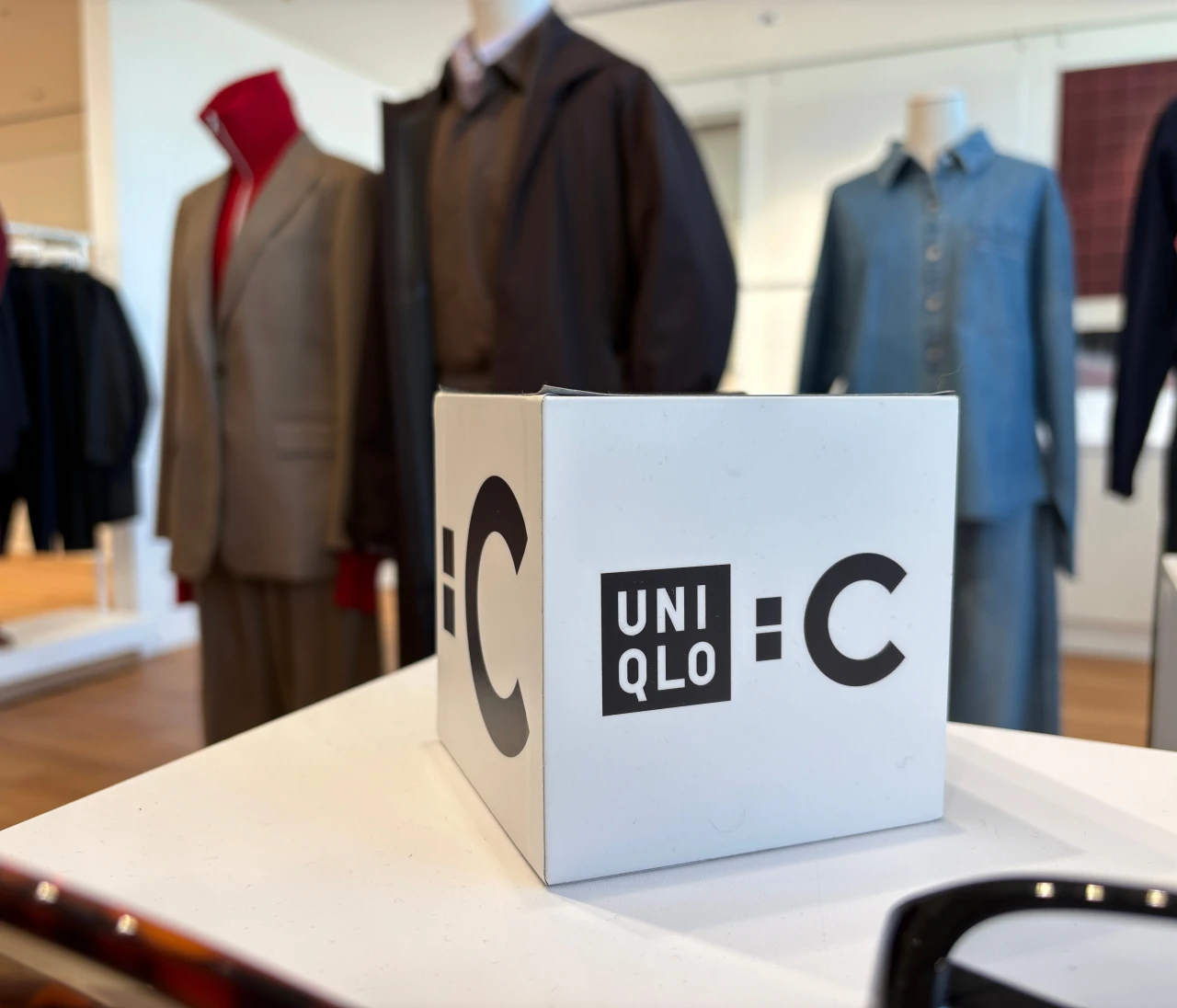義母との関係を読者にリサーチしたところ、関係が良好な人もいる一方で、その関係に悩んでいる人も多いことが判明。
読者から寄せられた義母とのトラブルや、義母に対してモヤモヤしたエピソードの中には、思わずギョッとしてしまうものも。子どもの名前を勝手に提案されたり、子どもができない責任を問われたり、古い価値観を押し付けてきたり…受け入れ難い義母の言動に対して、どう対応するべき!?
エッセイストの犬山紙子さんに、アドバイスをもらいました!
義母との「出産&子育て」モヤモヤエピソード
【エピソード1】義母が産まれてくる子どもの名前候補を勝手に考えていた(医療系・31歳)

maxim ibragimov/Shutterstock
「第一子妊娠中に義実家を訪れると、義母が産まれてくる子どもの名前候補を考えて待っていました。習字で書かれた名前候補を和室に並べられ『どれがいい?』と聞かれたときには唖然……。夫の『母さん考えてくれてありがとう』という雰囲気にのまれてしまい、結局は夫の出身地に因んだ名前に決定。今は家族3人で仲よく幸せに暮らしていますが、思い出すたびにモヤモヤしてしまいます」
「そのモヤモヤは今からでも夫に伝えるべき!」(犬山さん)
「これはお義母さんというよりも、夫の対応も気になってしまいました。お義母さんの行動は古い価値観に根付いたものなのかもしれないけれど、それに対して非を唱えないどころか感謝してしまうって…! きっと彼も、悪気はないと思うんです。ただ、お義母さんの教育によって“子どものことは夫側の家で決めるもの”という古い価値観を持っているのかもしれません。
今からでも、夫に不満を伝えていいと思います。このときの気持ちに少しでも折り合いをつけておかないと、この先、何かのタイミングで爆発してしまう可能性があるので。“私の意見も聞いてほしかった”とストレートに伝えられたらベストですが、妻と夫を逆転させて、他人のエピソードとして話すのも効果的。“妻側の母親が子どもの名前を用意していたんだよね”という話に、夫が“ヤバいね!”と反応したら、“あなたのお義母さんも同じことしたよね?”と。
彼自身の問題点に気づかせた上で、今後の対策も話し合えると安心ですね。こういうタイプのお義母さんは、子どもの子育てや学校選びなどにも口を出しかねません。そういう場合は、夫がお義母さんを制するべきであること、そして必ず自分と子どもの意見を聞いてほしいと、念を押しておきましょう」
【エピソード2】不妊治療中の傷つく発言。今でも悔しくて…(商社営業・34歳)

Ummi Hassian/Shutterstock
「不妊治療をしていた頃、まだ授かってもいない命に義母が勝手に名前をつけていました。そのうえ、『〇〇ちゃんと早く遊びたいわ〜』『あなたの家系は流産する家系なの?』とかなり精神的にダメージを受けるような言葉まで言われるようになりました。そのときは我慢してニコニコ受け流してしまったのですが、今思えば自己防衛のために失礼な発言であることを指摘すべきだったかなと悔しい気持ちでいっぱいです」
「確実に悪意のある発言をされたときは、距離を置く選択肢も」(犬山さん)
「相談者さんが悔しい気持ちになるのは当然ですし、よく我慢されたな…と。こんなことを言われたら、ショックで何も言えなくなるのが普通。言い返せなかった自分を責める必要はまったくありません。そもそもお義母さんの発言は、完全なる家系差別ですよね。そんなことをサラっと言ってしまう人の考え方を変えるのは、かなり難しいと予想します。なので、相談者さんが自分を守るためにはお義母さんとのつきあい方ではなく、距離を置く方法を考えてほしいです。
距離を置けない事情がある場合は、夫からお義母さんの発言を注意してもらいましょう。そして、お義母さんが発言の問題点を根本から理解し、きちんと反省した上で、謝罪してもらうことが第一歩だと思います。
妊娠・出産はセンシティブなトピックだという情報がこれほどあふれているのに、今も平気で聞く人がたくさんいますよね。私自身、結婚したら『子どもはいつ?』、娘が産まれたら『もう一人作ったほうがいいよ』などと、いろんな人から言われました。悪気はないにしても、配慮に欠けた発言を見過ごしたくない。言える相手なら指摘して、難しい相手なら意味深な表情で『ちょっと事情が…』と返すんです。相手に『いけないことを聞いてしまった』と気づきを与え、同じことを言われないように予防線を張っています」
【エピソード3】お宮参りの写真、誰が子どもを抱っこする?問題(システムエンジニア・34歳)

taka1022/Shutterstock
「娘の生後一カ月、私たち夫婦と両家の両親そろってお宮参りをしたときのこと。集合写真を撮る際、誰が子どもを抱っこするか?と写真を撮る前に揉めてしまいました。義母いわく「お産=穢れで、あなたはまだ子どもを抱っこするべきではない」とのこと。そのような言い伝えがあるのは知っていましたが、こんなに古いしきたりを重んじているとは驚きで…。この件以外にも義母が伝統を重視する姿が見受けられ、つきあい方に悩んでしまいます」
「夫から、お義母さんの知識をアップデートしてあげて」(犬山さん)
「伝統的な考えには女性蔑視にあたるものがありますよね。きっとお義母さんは、そういった考えを教えられてきたのでしょう。お義母さんに悪気がないとはいえ、もちろん相談者さんが我慢して従う必要はありません。相談者さんがお義母さんに異議を唱えるのは心の負担が大きいし、ややこしいことになりかねない。やはり最善策は、夫から伝えてもらうことだと思います。
義両親との距離感にもよりますが、今後も七五三やひなまつりといったイベントのたびに、価値観を押し付けられるのはストレスですよね。また、古いしきたりや伝統を重んじるタイプの義母は、傾向として、息子の妻に古きよき母親像を求めがち。口を出される前に、先手を打ちたいところです。
私ならば、現代のアップデートされた情報や意識を、夫を通じてお義母さんに共有します。たとえば、“昔は抱き癖がつくから子どもが泣いても抱っこしちゃだめだと言われてたけれど、最近はまったく違う研究結果があるみたいだよ”という感じに、エビデンスに基づいた記事を送ってみるとか。夫を介して、あくまで共有するスタンスでいれば、お義母さんも受け入れやすいはず!」
取材・文/中西彩乃







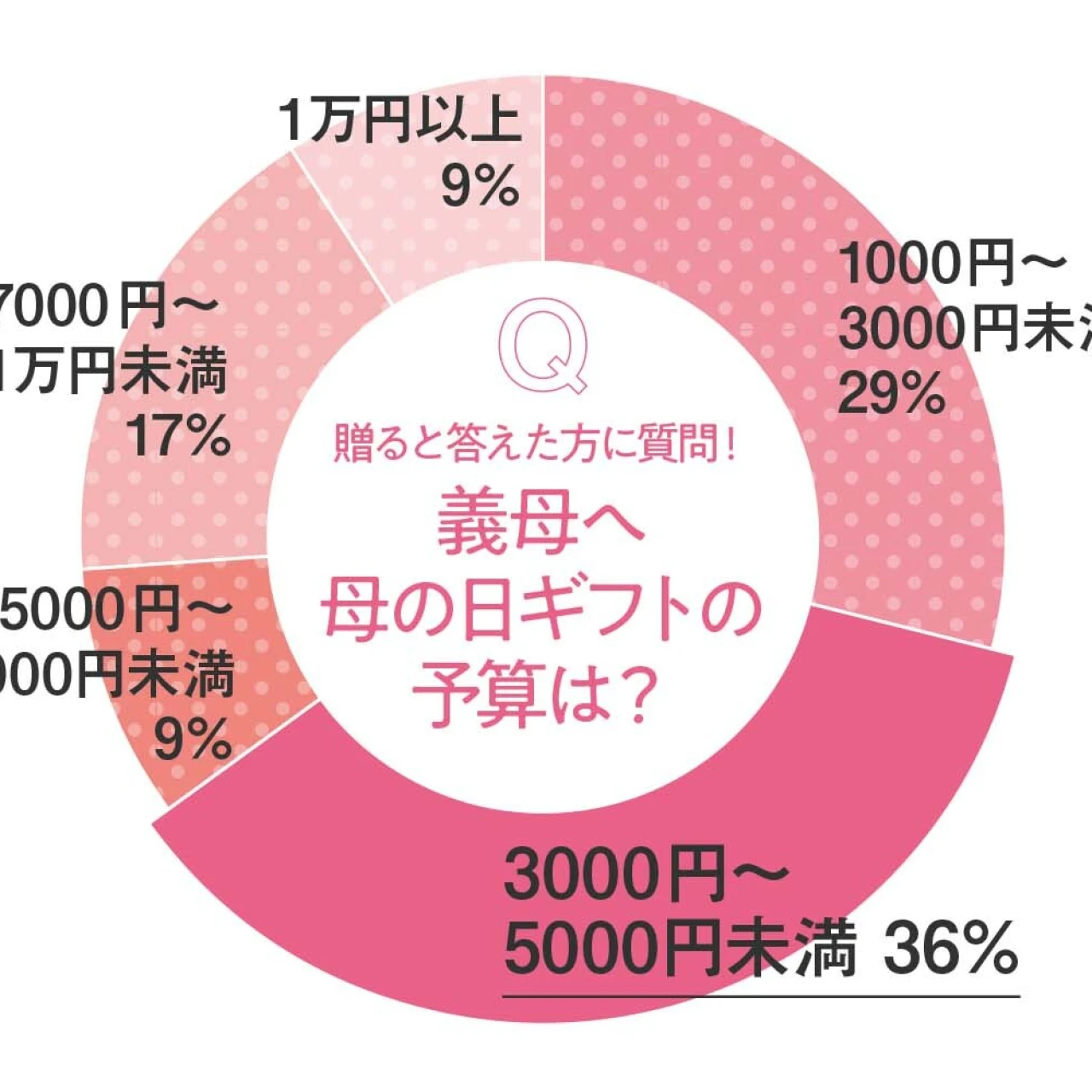





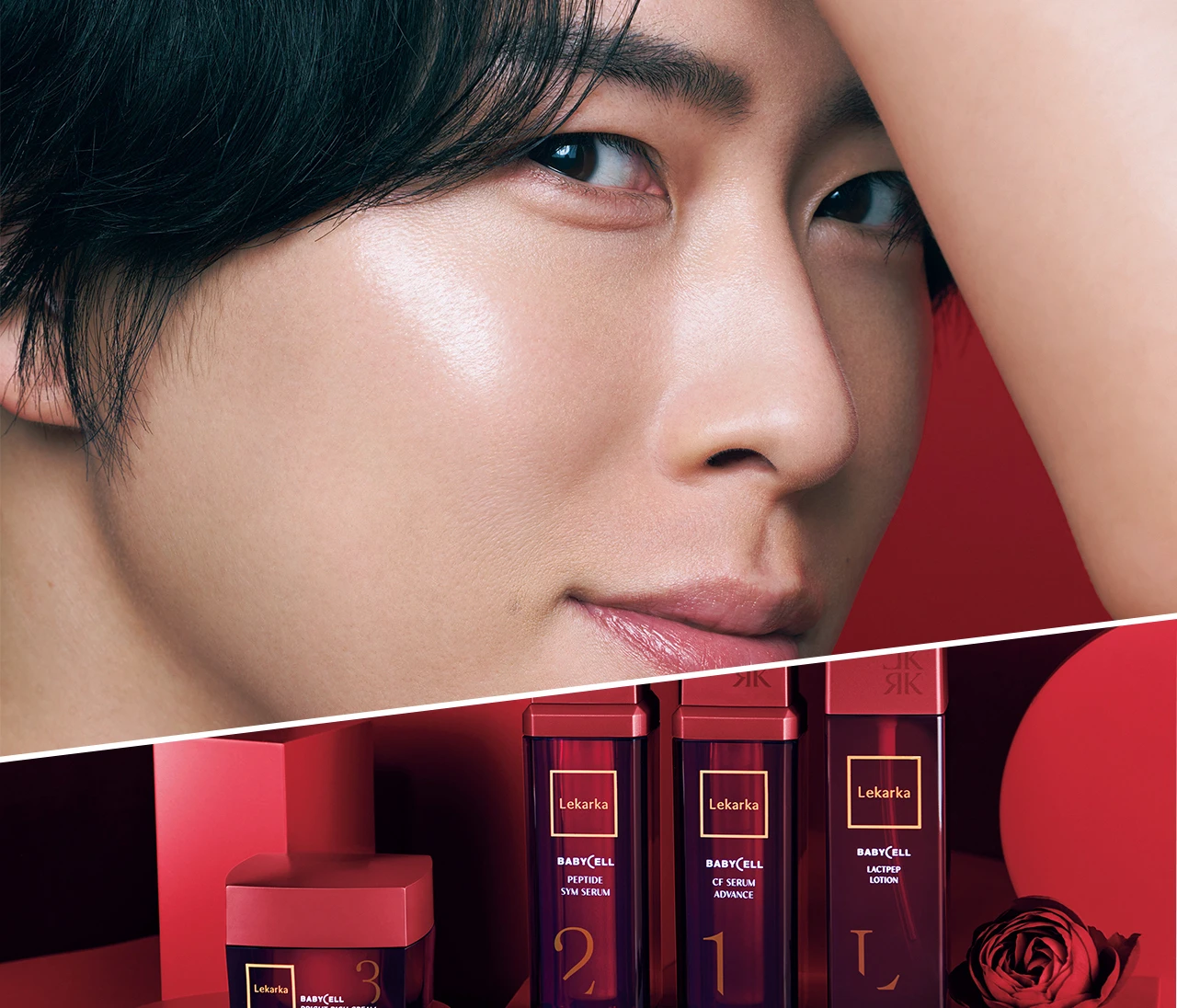













 Baila Channel
Baila Channel