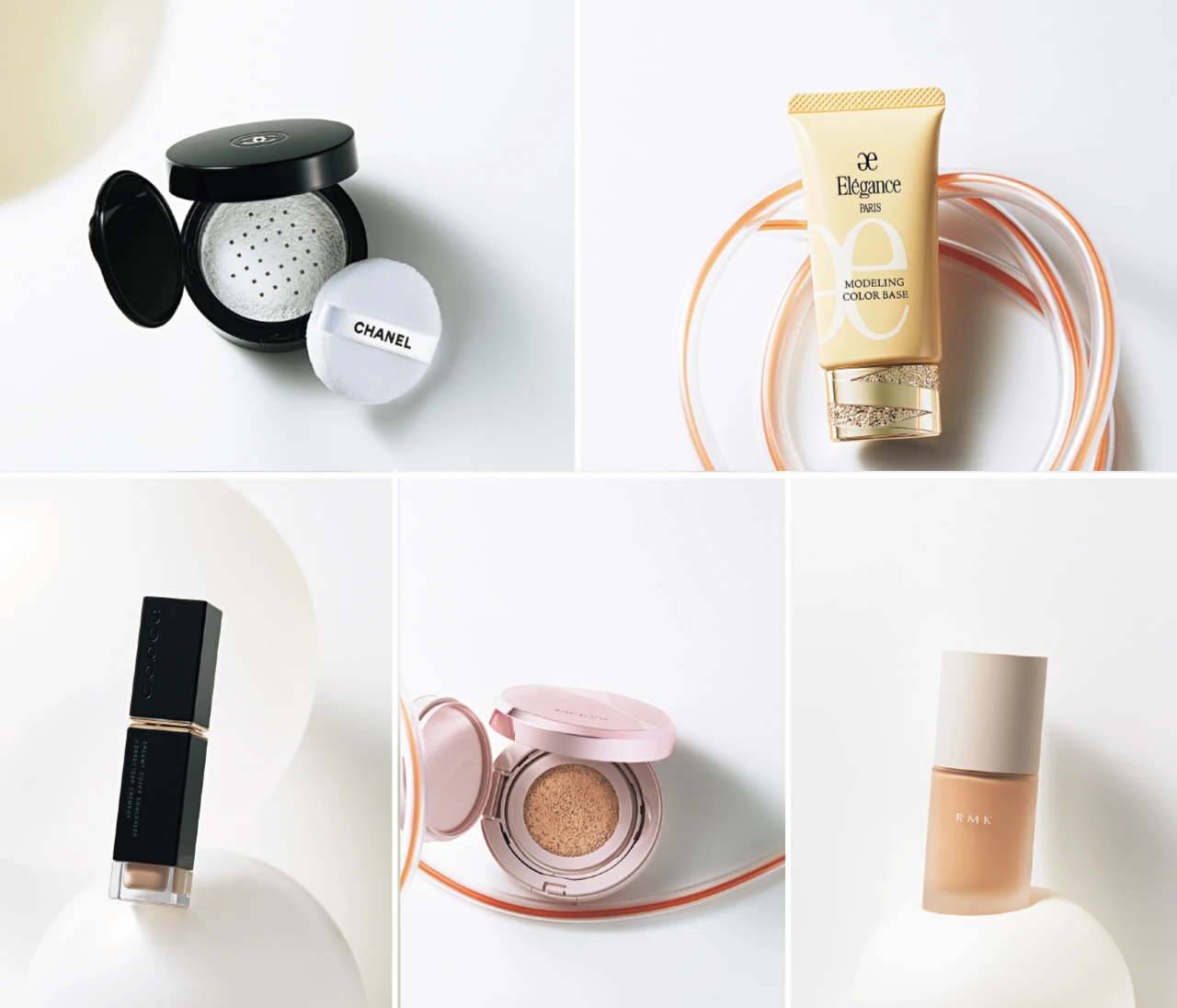BAILA創刊以来、本誌で映画コラムを執筆してくれている今祥枝(いま・さちえ)さん。ハリウッドの大作からミニシアター系まで、劇場公開・配信を問わず、“気づき”につながる作品を月2回ご紹介します。第16回は、イランの聖地で起きた連続娼婦殺害事件を描いた『聖地には蜘蛛が巣を張る』です。
イランで起きた娼婦連続殺人事件の恐るべき真相

テヘランから事件を追うためにやってきた女性ジャーナリスト、ラヒミ。演じるザーラ・アミール・エブラヒミ(兼アシスタント・プロデューサー、キャスティング)は、イランの国民的俳優として成功を収めていたが、2008年に第三者による私的なセックステープ流出により不当に職を追われ、フランスへ亡命して俳優を続けている。
読者の皆さま、こんにちは。
最新のエンターテインメント作品をご紹介しつつ、そこから読み取れる女性に関する問題意識や社会問題に焦点を当て、ゆるりと語っていくこの連載。第16回は、連続娼婦殺害事件から、イラン社会に根づくミソジニー(女性蔑視)に鋭く切り込む『聖地には蜘蛛が巣を張る』です。
2000年〜2001年に、イランのイスラム教シーア派の聖地マシュハドで起きた、16人もの娼婦が“スパイダー・キラー”と呼ばれる犯人に殺害された事件。映画はこの事件をモチーフに、犯人のサイード・ハナイ(メフディ・バジェスタニ)が「街を浄化する」という犯行声明のもと殺人を繰り返す中で、女性ジャーナリストのラヒミ(ザーラ・アミール・エブラヒミ)が、危険を顧みずに事件を追う姿を描きます。映画には殺害シーンなどの刺激の強い描写が含まれます。
監督はイラン出身で、北欧を拠点として活躍するアリ・アッバシ。この映画はイランでの撮影は叶わず、ヨルダンで行われました。それも当然だろうと思うのですが、映画でも描かれているように、犯人のサイード・ハナイが逮捕された際に、私たちの感覚からすると考えにくいことが起きたのです。
ハナイはイスラム教の敬虔な信者であり模範的な人物です。イラン・イラク戦争では兵士として青春時代を国に捧げました。イランの一部の市民や保守派メディアは、ハナイが「汚れた女たち」を街から始末した“英雄”だとして擁護したのです。イランという国家の暗部を浮き彫りにする題材に挑むことは、監督にとっても、特にイランで活躍する俳優たちにとってもリスクは大きく、相当な覚悟が必要だったでしょう。
映画では裁判の顛末も描かれているのですが、監督がこの事件を映画化しようと考えたのも、まさにこの点にあったといいます。それはハナイの物語を通して、イラン社会に根強くはびこるミソジニーの風潮について問題を提起するというものです。

殺害した娼婦を運ぶ犯人のサイード・ハナイ。自分の生きる意義、存在価値を確認するかのように娼婦たちを次々と殺害していく。
「娼婦だから殺されても仕方がない」という世間の偏見と差別

街角に立つ娼婦たちを利用しながら、いざとなると蔑む社会。そもそも女性に対する憎しみや蔑視を当然のこととする風潮が醸成されている地域で、どのようにしたら女性の尊厳や人権を守ることができるのか。
『聖地には蜘蛛が巣を張る』は、イランでは女性の人権や尊厳がないがしろにする現実が、当たり前のように社会に存在していることをよく伝えています。
被害者の家族は、娼婦などというふしだらなことをしているから殺されて当然だといった社会的制裁に不当に苦しめられています。女性たちが娼婦として街角に立つ理由は、様々です。そもそも、このような女性蔑視がまかり通る社会で、本作に登場する女性のように、シングルマザーや養わなければならない家族がいるのに仕事がない女性の場合、生活費を稼ぐための選択肢が多いとは言えないでしょう。
一方で、ここまであからさまではないにせよ、「そんな格好をしているから、そんな仕事をしているから、だからひどい目に遭っても仕方がない」といった世間の風潮、自己責任論や偏見や差別は、日本でもほかの国でも珍しいことではありません。
もちろん、何かしらのステレオタイプは誰の中にも存在するでしょう。私自身、「○○だから、そういう目に遭う可能性は高くなるのは当然なのでは」といった考え方を一瞬でもしてしまうことはあります。そういうときには、一度立ち止まってみる必要がある、自分の中のステレオタイプを自覚することの必要性を、常に感じています。どう考えても、悪いのは加害者の方であって、責められるべきは被害者とその関係者では決してないのです。
ミソジニー(女性蔑視)は当たり前のように存在している

犯人のサイード・ハナイが逮捕された際、彼を英雄視する一部の人々の考え方は、確実に次の世代へと受け継がれていく。負の遺産を継承しないためにも、大人が取るべき態度、果たすべき役割とは?
アッバシ監督は本作の製作意図について、「ミゾジニーは、宗教や政治が理由というわけではなく(中略)、国に限らず、人々の習慣の中で植えつけられる」と語っています。例えばイランには、昔から女性を憎むべき対象とする考えがあるそうですが、そうした価値観は連綿と継承され、社会に根づいている。だからこそ、一朝一夕には変えられない、厄介で深刻な問題なのです。
犯人のハナイは戦争でひどく傷ついた被害者でもあり、戦争で何かを変えることはできなかった、自分は国にとって必要不可欠な人間ではなかったという挫折感を抱いています。そこから再び人生に意義を見出すかのように、宗教的な啓示によって娼婦を排除するという使命を遂行します。そこには、家長としての尊厳を損なわれていると感じている男性としてのプライド、あるいは呪縛も感じられます。
家父長制が女性の尊厳や人権を剥奪するという問題は、特に近年はアジア作品でもよく目にするテーマです。それはまた、「男性とはこうあるべきもの」とするステレオタイプによる男性の生きづらさとも表裏一体でしょう。
私がこの映画で真に恐ろしいと感じたのは、こうした価値観、ミソジニーや家父長制が当たり前のように子どもの代に受け継がれていく“負の連鎖”です。親の価値観や憎しみ、虐待などが負の連鎖として、子供の代にも受け継がれていくことは、様々なケースで目にしますよね。どうやったら負の連鎖を断ち切ることができるのか。これは大人たちに責任があり、自覚的になるべき問題でしょう。
一方で、この映画はイラン社会には多様な意見があること、またステレオタイプではない女性像も示そうとしています。アッバシ監督は、イランの女性を「ヒジャブを着用した禁欲的な女性」としてのみ、イメージさせるような映画が多すぎるとも指摘しています。人種、宗教に対するステレオタイプもまた、私たちの中に根強くあることにあらためて気づかされる映画でもあります。

数々の苦難を乗り越えながら、ついに裁判に臨むラヒミ。警察でも裁判所でも、行く先々で「女性である」というだけで、男性たちに理不尽に侮蔑的な態度を取られながらも、それをうまくかわす術を発揮する姿に複雑な思いも。
『聖地には蜘蛛が巣を張る』4月14日(金)より、新宿シネマカリテ、ヒューマントラストシネマ渋谷、TOHOシネマズシャンテほか 全国ロードショー
監督:アリ・アッバシ
出演:メフディ・バジェスタニ、ザーラ・アミール・エブラヒミ、アラシュ・アシュティアニほか


























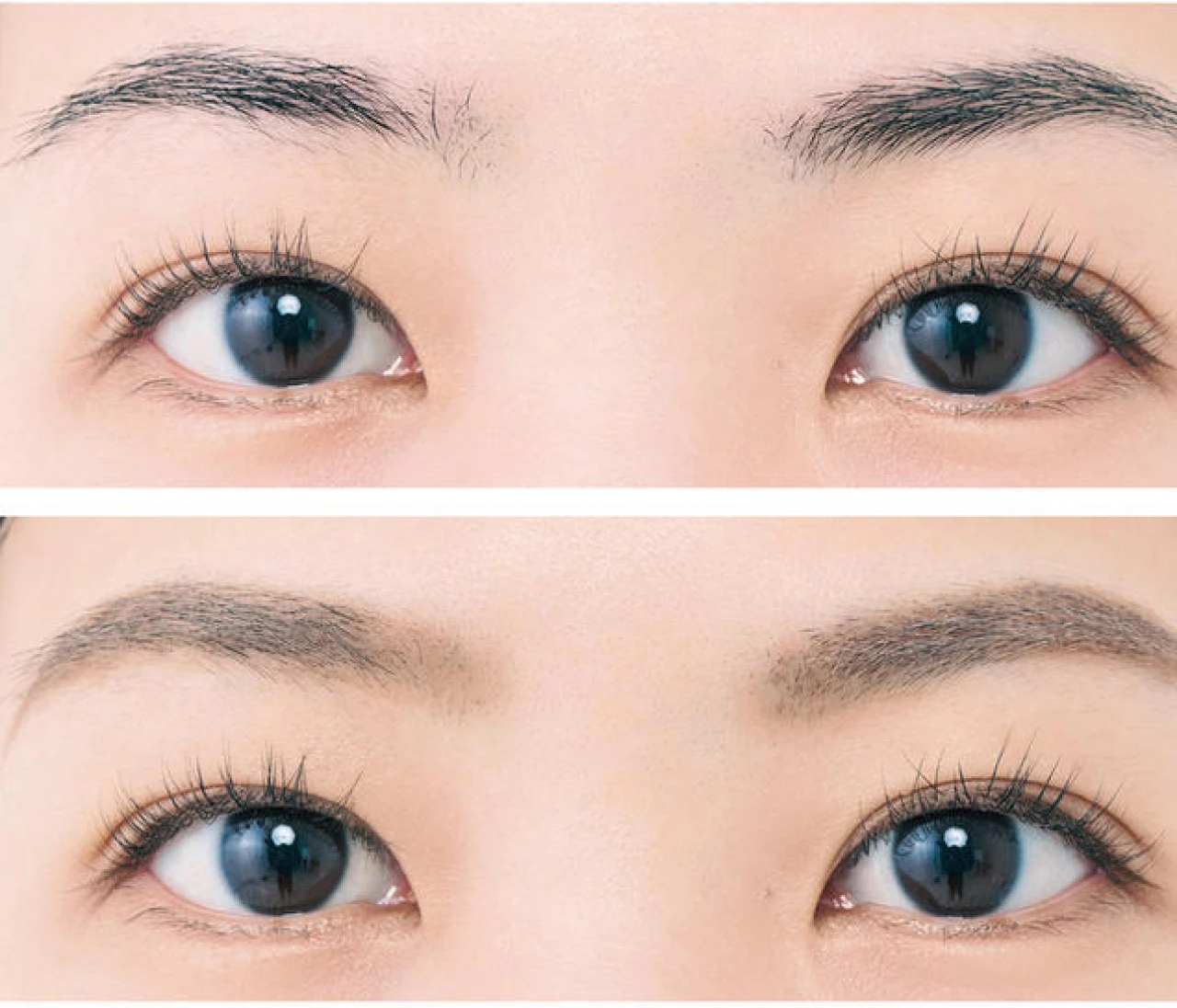







 Baila Channel
Baila Channel




![大人の肌見せはデコルテ&ウエストをのぞかせる「バタフライシルエット」でかっこよく![ヘアアレンジ付き]](https://img-baila.hpplus.jp/image/b4/b4780bfc-9f41-4f6e-8046-09244547f914-1280x1096.jpg)